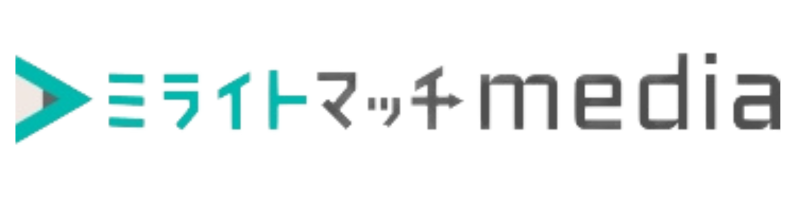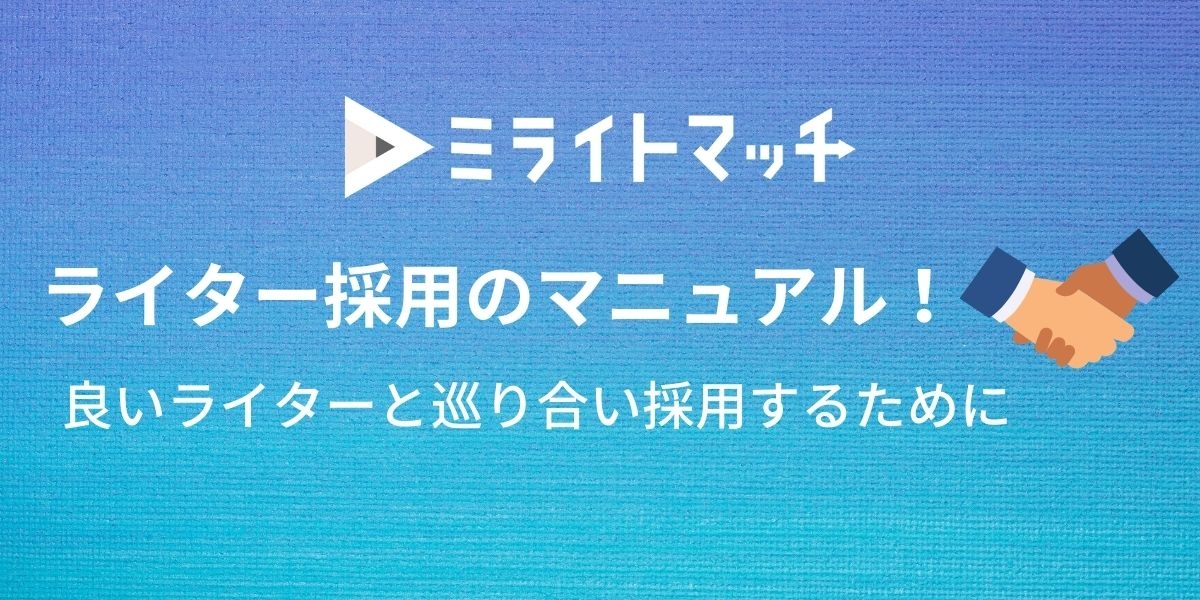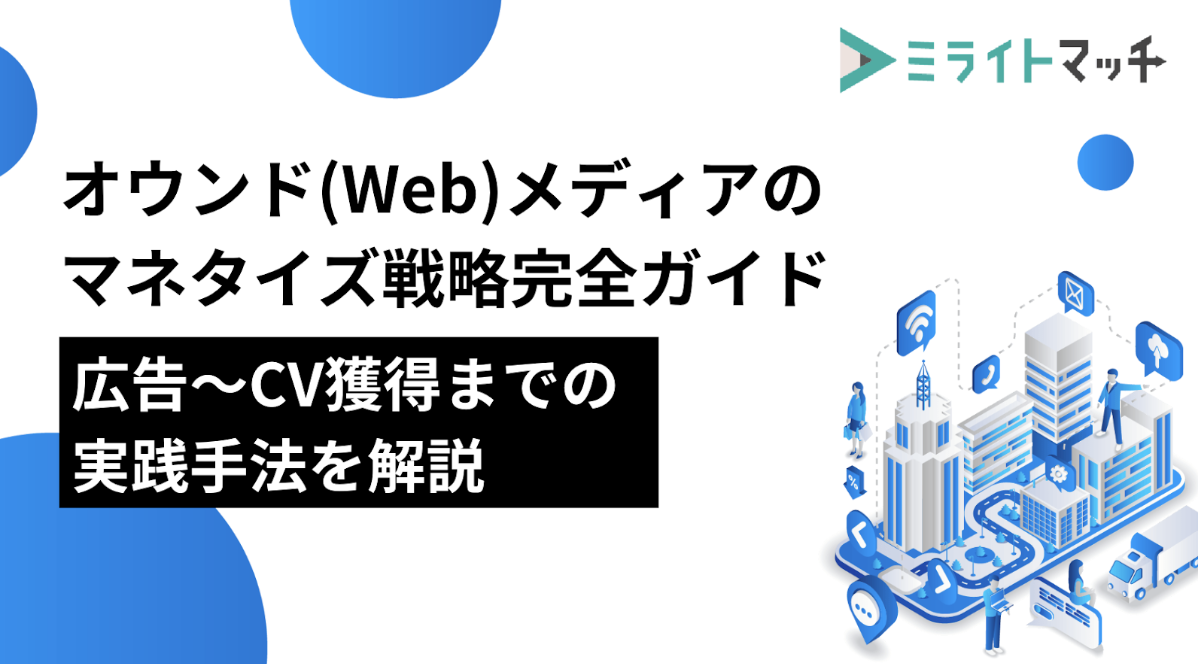
近年、企業のマーケティング施策として、Webメディア(オウンドメディア)を活用する企業が急増しています。
しかし、PVは伸びても収益化につながらない、営業との連携が取れていないという声も多く聞かれます。
本記事では、オウンドメディアビジネスを前提にした「Webメディアのマネタイズ戦略」を徹底解説します。
広告・アフィリエイトといった王道施策から、ホワイトペーパーやリード獲得を目的とした設計、さらにはKPI管理まで、実例と共にご紹介します。
- Webメディアの種類
- オウンドメディアのマネタイズ戦略
- WEBメディアのマネタイズ手段
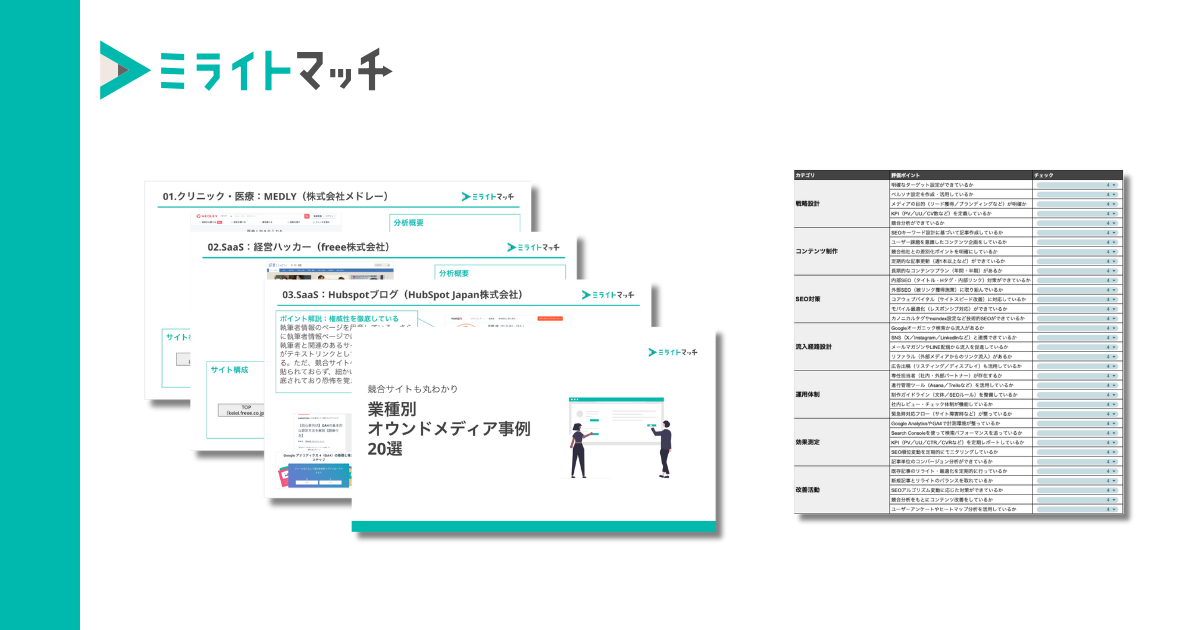
Webメディアの種類と運営する上でのポイント
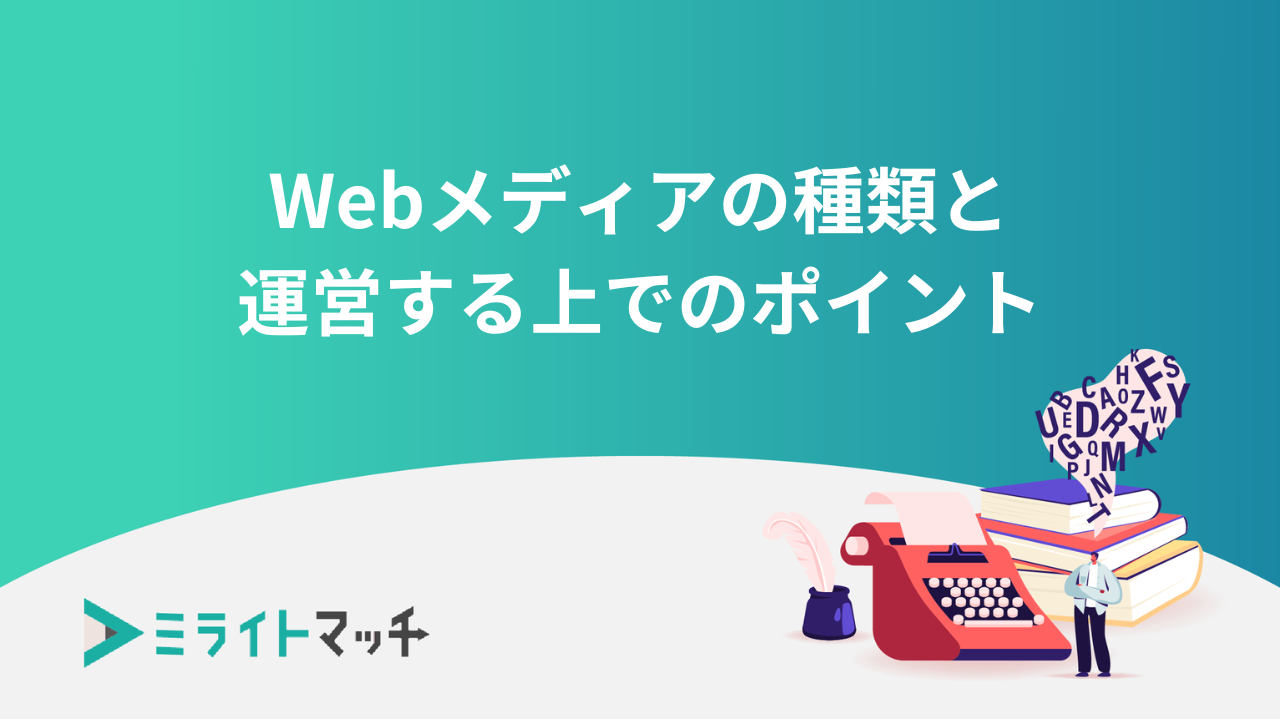
企業の情報発信において、Webメディアは信頼獲得からリード獲得、ブランディングまで幅広く貢献します。ただし、目的に合ったメディア形式を選ばなければ、時間とコストばかりがかかって成果に結びつかないという課題も少なくありません。
ここでは、Webメディアを「一次情報型」「二次情報型」「オウンドメディア」「キュレーション型」「SNS運用型」の5種に分類し、それぞれの特徴と運用時の注意点を整理します。
| 見出し | 特徴 | メリット | デメリット | 活用目的 |
| ①一次メディア(1次メディア) | 自社が直接得た情報を発信する。例:事例紹介、独自調査、インタビュー等。信頼性が高い。 | 情報の信頼性が高く、ブランディング効果がある。差別化しやすい。 | 情報収集・編集に手間がかかる。継続的な発信にはリソースが必要。 | BtoBでの信頼獲得・専門性のアピール |
| ②二次メディア(2次メディア) | 他社情報をもとに再編集・要約して発信。例:業界ニュースまとめ、比較記事など。 | SEOに強く、コンテンツ量を確保しやすい。短期間での立ち上げが可能。 | 情報の独自性が弱く、権威性に欠ける場合がある。 | SEO流入・業界全体の俯瞰・比較情報の提供 |
| ③オウンドメディア | 自社運営の情報発信メディア。リード獲得に最適。導線設計や資料DLと相性が良い。 | リード獲得、顧客教育、ブランディングが同時にできる。資産性が高い。 | 成果が出るまでに時間がかかる。コンテンツ戦略・設計が重要。 | 中長期のリード育成・コンバージョン獲得 |
| ④キュレーションメディア | 他社コンテンツの要点をまとめて紹介。SEOに強い一覧・まとめ記事が中心。 | 少ない労力で多くのコンテンツを作成可能。情報収集が容易。 | 独自性が乏しく、専門性・信頼性には欠ける。リード獲得には不向き。 | トレンド把握・SEO集客・ライトな読者向け |
| ⑤SNS(ソーシャルメディア) | 短文・画像・動画などで認知拡大。拡散力が高く、短期的効果に強い。 | 拡散性が高く、リアルタイムな反応が得られる。ファン形成に有効。 | アルゴリズムの変動や炎上リスクあり。資産性が低く、長期施策には不向き。 | 認知拡大・交流・コンテンツ導線への誘導 |
①1次メディア
一次メディアとは、自社が主体となって得た情報やデータを元に発信するメディアです。代表例としては、以下のようなコンテンツがあります:
- 自社で実施したアンケート・調査レポート
- 顧客インタビュー・導入事例
- 自社サービスの運用データ・改善結果
こうした情報は独自性が高く、業界内での信頼性や権威性を高める上で有効です。特にBtoBビジネスにおいては、エビデンスベースの情報が評価されやすいため、営業資料・ホワイトペーパーとしての再利用も可能です。
②2次メディア
二次メディアとは、他社が公開しているニュースや調査、統計情報を引用・整理し、自社視点で再編集して発信するメディア形式です。
たとえば、
- 業界ニュースの週間まとめ
- 各社サービスの機能比較・料金比較
- トレンド解説+専門家コメント
などが挙げられます。
SEOの文脈で非常に有効な形式であり、検索流入を短期間で伸ばしやすい一方、一次情報に比べると差別化や専門性の訴求が弱くなる傾向もあります。
③オウンドメディア
オウンドメディアは、自社ドメインで構築・運営されるWebメディアの総称です。特にBtoBマーケティングとの親和性が高く、ホワイトペーパーや資料請求といったリード獲得との導線設計が容易な点が強みです。
構成要素には以下のようなものがあります。
- SEOを意識した記事コンテンツ
- CTA(行動喚起)付きのフォーム導線
- 事例・導入実績ページと連動したナビゲーション設計
正しく運用すれば「集客→教育→案件化」までをWeb上で自動化できる資産型施策として機能します。
④キュレーションメディア
キュレーションメディアは、既存の情報を「一覧形式」「まとめ記事」として整理・再構成したメディアです。例としては、
- 「◯◯業界の注目サービス10選」
- 「2025年注目のトレンドキーワードまとめ」
- 「◯◯の成功事例から学ぶ〜」
といったスタイルです。
SEO上では効果を発揮しやすく、比較的早い段階でアクセスを稼ぎやすい一方で、情報の独自性が低く、リード獲得などの深いアクションにはつながりにくい傾向があります。
⑤SNS(ソーシャルメディア)
SNSはWebメディアの主役というより、補完的な認知拡大・信頼構築のチャネルとして活用されるのが理想です。
X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなど媒体によって適したターゲット・投稿形式が異なり、以下のように使い分けが重要です。
| SNS媒体 | 得意な用途 | 向いているコンテンツ |
| X(旧Twitter) | トレンド発信・速報性のある情報 | カジュアルな意見・日常の裏話・速報性のある業界ネタなど |
| 視覚訴求・ブランディング | デザイン性の高い商品、写真映えするビジュアルコンテンツ | |
| BtoB・ビジネス向けの信頼構築 | 導入事例、業界知見、採用情報、経営者の発信など | |
| TikTok | エンタメ性・認知拡大・若年層向けの訴求 | ショート動画によるストーリー、商品紹介、ビフォーアフター系など |
| コミュニティ構築・既存顧客との関係維持 | ニュース・イベント告知、ブログ更新の共有、長文投稿、グループ運用など |
メディアのマネタイズ(収益化)方法8選|収益化の全体像と選び方のポイント
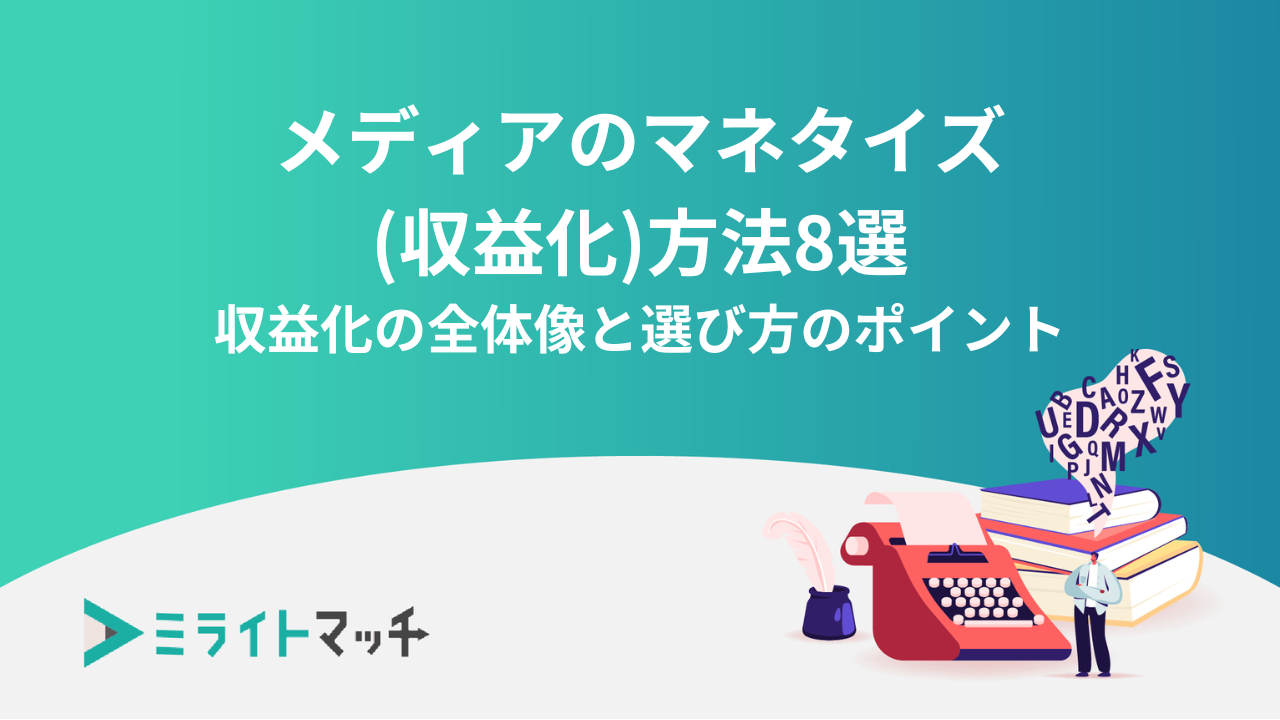
Webメディア運営において、情報発信と並んで重要なのが「収益化(マネタイズ)」です。広告だけでなく、サービス販売や有料コンテンツなど、手段は多様化しています。
メディアの収益化には「即効性のあるモデル(アフィリエイト・アドネットワーク)」と、「長期的に育てるモデル(有料化・サブスク・サービス販売)」があります。重要なのは、自社メディアの強みと成長段階に応じて、最適なマネタイズ手法を選ぶことです。
たとえば、
- 立ち上げ初期 → アドネットワーク・アフィリエイト
- PV安定期 → 純広告・記事広告
- ブランディング確立後 → サービス販売・有料化・サブスク
というように、段階に応じてマネタイズをシフトさせていく設計が成果につながります。
代表的な8つの収益化モデルについて、それぞれの仕組み・メリット・注意点を詳しく解説します。媒体の特性やターゲットに応じて最適な方法を選びましょう。
マネタイズ手段①「広告収入」
広告は、最も導入しやすくメジャーなマネタイズ手段です。メディア内に広告枠を設け、クリックや表示、成果に応じて収益を得ます。広告モデルには以下の3つがあります。
広告収入①-1「純広告」

純広告とは、特定の広告主が直接出稿する形式の広告です。通常はバナーやタイアップなどで、契約期間・表示回数に応じて定額で掲載されます。
- メリット:単価が高く、ブランディング効果も見込める
- デメリット:営業力・信頼性が必要。直接契約のハードルが高い
- 向いているメディア:業界特化型メディア、大型ポータルサイト、企業運営のオウンドメディアなど
広告収入①-2「アフィリエイト」
アフィリエイト広告は、成果報酬型の広告です。
読者が記事内リンクを経由して商品購入や申込をすると、報酬が発生します。
- メリット:クリックではなく“成果”に応じて収益化できる
- デメリット:訴求力のあるライティングスキルが求められる
- 向いているメディア:レビューサイト、比較記事、特化ブログなど
アフィリエイトを活用したメディア成功事例として、株式会社スペースキーが運営する国内最大級のキャンプメディア「CAMP HACK」があります。

「CAMP HACK」は、アウトドアの最新トレンドやイベント、ファッションなど、さまざまなシーンを通じてあらゆる“アウトドア人”が満足できる内容を発信するアウトドア専門のWebメディアです。
月間利用者数は340万人、月間総PV数は2,480万PV、またSNS総フォロワー数においては42万人のファンを抱え、さらに年間読者数は2,100万人と、年間キャンプ利用人口730万人を大幅に超えています。
サイトの構成を見ると、関連キーワード~商品名までを網羅的に拾い上げ、検索順位の上昇を狙っていることが分かります。
広告収入①-3「アドネットワーク」
アドネットワークは、Google AdSense などの自動広告配信サービスです。PVに比例して収益が発生するため、アクセス数が収益の鍵になります。
- メリット:簡単に導入でき、管理の手間が少ない
- デメリット:単価が低く、アクセス依存度が高い
- 向いているメディア:ニュース系・雑記ブログ・大量PVメディア
マネタイズ手段②「記事広告(タイアップ広告)」
記事広告は、企業の商品やサービスを取材・紹介する形での記事広告です。企業側のマーケティング戦略の一環として発注されることが多く、1本あたり数万円〜数十万円の収益が見込めます。
- メリット:単価が高く、継続受注すれば安定収益になる
- デメリット:読者に「広告感」を与えないライティング技術が必要
- 向いているメディア:影響力のある特化メディア、BtoBオウンドメディア
「記事(タイアップ)広告」を活用したマネタイズ成功事例として、株式会社マイベストが運営する「my best」があります。

「my best」は以下のコンセプトで、おすすめ情報を発信しているサイトです。
”実際に商品を購入して自社の施設で比較検証したり、専門家を中心としたクリエイターが自らの愛用品やおすすめ商品を紹介して、あなたの“選ぶ”をお手伝いします”
アフィリエイトサイトとしての一面もありますが、メインの収入はBtoBのタイアップ広告であり、そのPV数は月間3000万を超えます。
公開されているタイアップ広告の相場を参考にすると、「my best」では、1か月間、1つのPR広告を掲載すると100万、200万円以上の収益化に成功していると判断できます。
マネタイズ手段③「コンテンツの有料化」
特定のノウハウや情報を有料コンテンツとして販売するモデルです。電子書籍、PDFレポート、会員限定記事、動画コンテンツなど、形式は多岐に渡ります。
- メリット:リピート性があり、コンテンツの資産化が可能
- デメリット:無料情報との差別化が必要。販売導線設計も重要
- 向いているメディア:専門性の高いブログ・業界分析メディア・教育系メディア
「コンテンツの有料化」を活用したマネタイズ成功事例として、人気占い師・作家であるしいたけ.さんが運営する「しいたけ占いのしいたけ.」があります。
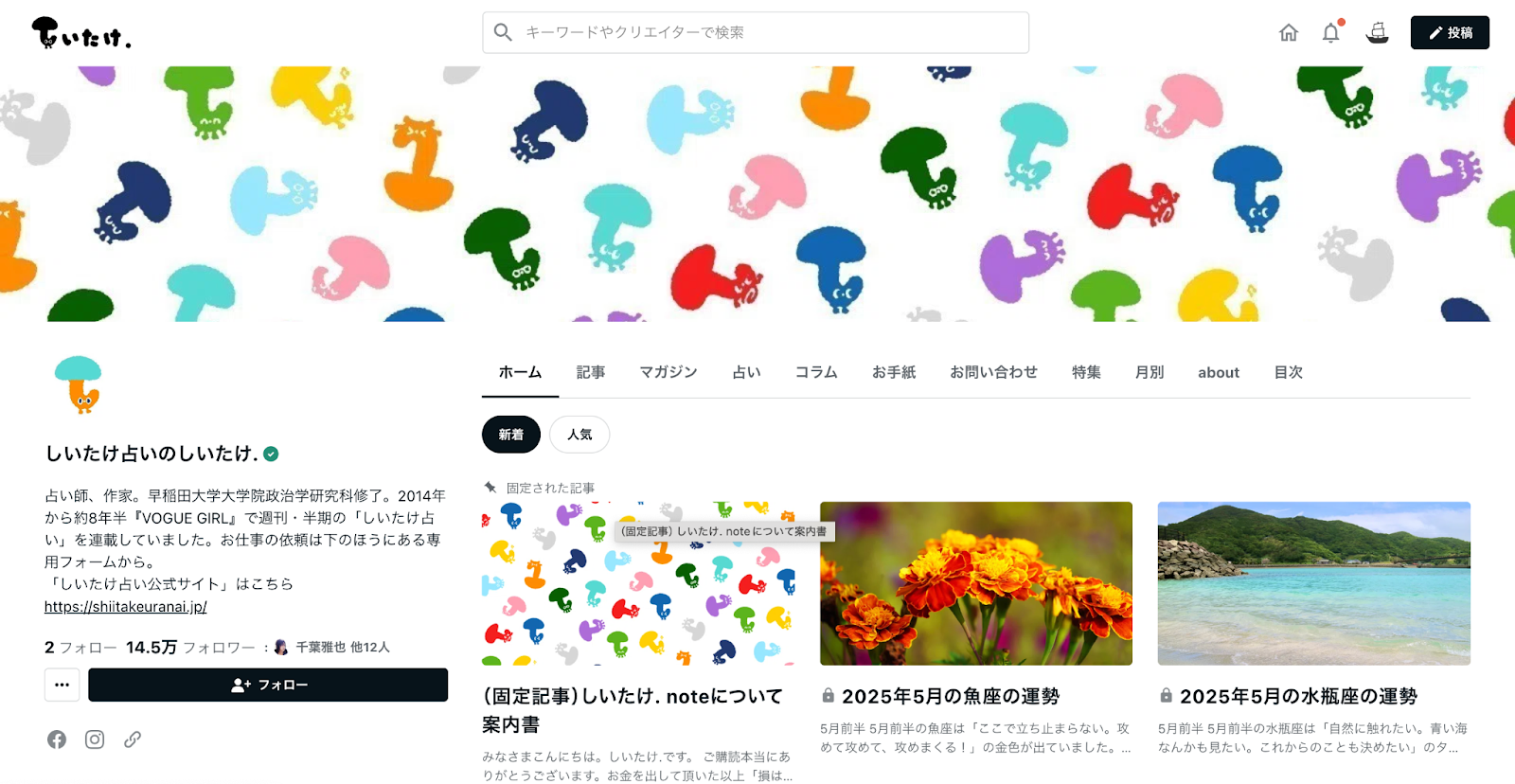
しいたけ.さんは占星術とオーラカラーを組み合わせた独自の占いスタイルを確立しています。
単なる運勢の予測にとどまらず、読者の心に寄り添うような温かみのある文章で、多くのファンを魅了しています。このような高品質なコンテンツが、ユーザーに「お金を払ってでも読みたい」と思わせる価値を提供しています。
「しいたけ占い」では、週刊の占いを無料で提供し、月刊や半期の詳細な占いを有料で提供するという、無料と有料のコンテンツをバランスよく配置しています。
- 月刊12星座占いパック(¥980/月):12星座すべての月刊占いをまとめて購読できるパック。
- 星座別の月刊占い(各¥500/月):特定の星座に特化した月刊占い。
- しいたけ.サロン コラム(¥500/月):週1回更新されるコラムマガジン。
- お手紙・お悩み相談(¥300/月):読者からの悩みに答える形式のコラム。
新規ユーザーが無料コンテンツで興味を持ち、より深い内容を求めて有料コンテンツに移行する自然な導線が構築されています。
マネタイズ手段④「売却」
一定のPVや収益を持つメディアは、他社に売却することも可能です。買収側にとっては、すぐに収益化できる資産として価値があります。
- メリット:まとまった金額が一度に得られる
- デメリット:継続的な収益ではなく、一度限りの収益化となる
- 向いているメディア:特化ジャンルでSEO評価が高いメディア、コミュニティ性のあるサイト
「Webメディア売却」の成功事例として、2020年、株式会社プルチーノが漫画紹介メディア「漫画大陸」を2億2000万円で、株式会社リアルワールドに譲渡した事例があります。
月間約600万PVを達成する「漫画大陸」は公式の漫画アプリ・電子書籍サイトへの導線を担う役割のWebメディアです。
「漫画を含めたエンタメコンテンツ全領域においてユーザーとコンテンツをつなぐマッチングメディアプラットフォームを形成しています。
「シェアNo.1を目指す」と公言している株式会社リアルワールドが、事業開拓を狙い譲り受けた事例です。
マネタイズ手段⑤自社商品・サービス販売
自社の商品やサービスをメディアを通じて販売する方法です。D2CブランドやSaaS、講座販売など、コンテンツと自社プロダクトを連動させた設計が効果的です。
- メリット:利益率が高く、LTV(顧客生涯価値)を高めやすい
- デメリット:商品開発や販売体制の構築にコストがかかる
- 向いているメディア:ブランドメディア、コーポレートメディア、教育メディアなど
自社商品・サービス販売でマネタイズしたメディアの成功事例として、北欧、暮らしの道具店(株式会社クラシコム)があります。
オウンドメディアの影響力を活用し、他社とのコラボレーションによるブランデッドコンテンツや広告事業も展開しています。
ユーザーの96%が週に1回以上サイトを訪問し、そのうち72%が毎日閲覧しているというデータが示すように、強固なユーザー基盤を築いています。
また、コンテンツマーケティングの効果により、2012年には前年比175%の売上増加を達成し、年商2億1千万円を記録しています。
北欧雑貨やインテリアを扱うECサイトで、スタッフの愛用品や商品エピソードを紹介するコラム記事を掲載し、
マネタイズ手段⑥マッチングサービス
メディアを介して、ユーザー同士やユーザーと企業をつなぐマッチング型サービスを提供するモデルです。求人・不動産・士業紹介などが代表例です。
- メリット:成約時に高単価の成果報酬が得られる
- デメリット:成約数の安定化が難しい。運用に人手がかかる
- 向いているメディア:地域情報サイト、スキルマッチング系、専門相談メディア
マッチングサービスの成功事例として、リクルートが運営する不動産情報サイトのSUUMO(スーモ)があります。
物件情報の掲載料や広告収入で、豊富な物件情報と使いやすい検索機能により、多くのユーザーを獲得し、掲載企業からの収益を確保しています。
AWSの大規模な機械学習基盤「Crois」を活用し、パーソナライズされた物件推薦システムを実現しています。
駅や沿線、価格帯などの条件で物件を検索できる機能を導入し、ユーザーの利便性を高めました。
SUUMOを含む住宅・不動産領域は、リクルートのマッチング&ソリューション事業の約30%の収益を占める主要な収益源となっています。
マネタイズ手段⑦サブスクリプション
継続的な情報やサービスを提供し、月額課金で安定収益を得るモデルです。メディア×サブスクの例としては、有料メルマガや会員限定フォーラム、LINE配信などが挙げられます。
- メリット:ストック型の安定収益が見込める
- デメリット:継続利用のためのコンテンツ更新・運用体制が必須
- 向いているメディア:教育・ビジネス・マニア層向けのメディア
サブスクリプションの成功事例として、有機野菜や食材の定期宅配サービスのOisix(オイシックス)が挙げられます。
オイシックスは、有機野菜やミールキットを定期的に宅配するサブスクリプション型の食品ECサービスを提供しています。
20分で2品作れる「Kit Oisix」など、忙しい家庭向けの時短商品を開発し、顧客のニーズに応えています。
2025年3月期第1四半期には、BtoCサブスクリプション事業の利益率が前年同期比で2.5ポイント改善し、安定した収益基盤を確立しています。
マネタイズ手段⑧ドロップシッピング
在庫を持たずにネットショップを開設し、メディア上で商品を販売する手法です。注文が入ると、提携先が自動で発送を行います。
- メリット:仕入れリスクがゼロ。手軽に物販をスタート可能
- デメリット:利益率が低く、リピーター戦略が立てづらい
- 向いているメディア:ライフスタイルメディア、ガジェット紹介ブログなど
ドロップシッピングの成功事例として、バブルティーのぬいぐるみなどを販売するオンラインストアのSubtle Asian Treats(サブトル・アジアン・トリーツ)が挙げられます。
Subtle Asian Treatsは、マレーシア出身のTze Hing Chan氏が立ち上げたドロップシッピング型のオンラインストアで、バブルティー(タピオカミルクティー)をモチーフにしたぬいぐるみなどを販売しています。
アジア系コミュニティで人気のバブルティーをテーマにした商品をいち早く取り入れ、ニッチな市場を開拓しました。
実際に、立ち上げから2か月で約19,000ドルの利益を上げ、最終的には10万ドルの売上を達成しました。
ニッチな商品選定とSNSを活用したマーケティングにより、短期間で高収益を実現しています。
メディアマネタイズの成果を最大化するKPI設計と導線設計
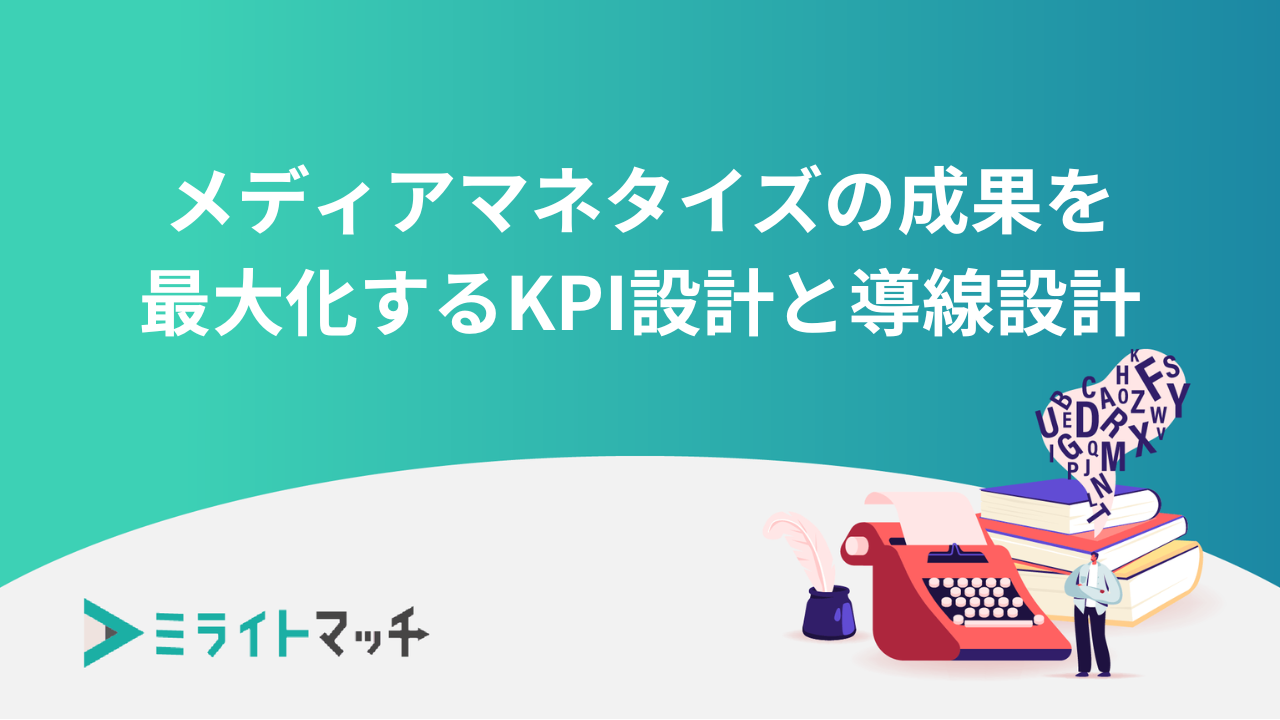
Webメディアを通じて収益化を目指す際、ただコンテンツを量産するだけでは成果に結びつきません。重要なのは「収益直結のKPI設定」と「コンバージョンまでの導線設計」です。
PV数やSNSのフォロワー数はあくまで表面的な指標。収益を生み出すには、読者の“行動”にフォーカスした設計が求められます。
PV数だけでは意味がない?重要KPIの考え方
PV(ページビュー)はあくまで“注目度”を測る指標に過ぎません。収益性を高めるには、以下のような「行動を伴うKPI」に目を向ける必要があります。
| KPI指標 | 説明 | 目的 |
| CV率(コンバージョン率) | 訪問者のうち、CTAを経由して成果に至った割合 | 成果につながる導線が機能しているかを把握 |
| リード獲得単価(CPL) | 1件の見込み顧客を獲得するのにかかったコスト | 広告・SEO施策の効率性の評価 |
| CTAクリック率 | CTAボタンがどれだけの確率でクリックされているか | 訴求メッセージや導線設計の評価 |
| 記事別CV貢献率 | 各記事が最終的なコンバージョンにどれだけ貢献しているか | 収益に直結する記事の選別・強化 |
KPIは“読みやすさ”や“拡散性”よりも、「売上・獲得」などビジネス的な出口に近い指標を最優先で設計するのが鉄則です。
リード獲得率と営業転換率を上げるCTA設計
どれだけ読まれる記事を書いても、CTAが弱ければ収益化はできません。
CTA(Call To Action)は、読者の関心が最も高まった瞬間に提示する“次の一手”です。記事構成との一貫性と、読者の心理段階に応じた設計が欠かせません。
| タイミング | CTA例(BtoB向け) | 読者の心理状態 |
| 導入直後 | 資料ダウンロード / 事例集の無料配布 | 興味段階:軽く情報収集をしている |
| 本文中盤 | ホワイトペーパー請求 / 無料診断 | 比較検討段階:課題を自覚し始めた |
| 記事末尾 | 無料相談申込 / お問い合わせフォーム | 顕在ニーズ段階:行動に移す寸前 |
CVポイント(ホワイトペーパーDL、無料相談予約など)の作り方
コンバージョン(CV)を最大化するには、「読者が自然にアクションしたくなる導線」×「魅力的なオファー」の設計が重要です。
| CVポイント | 説明 | 向いている読者段階 |
| ホワイトペーパーDL | 業界課題・事例・導入効果などをまとめたレポート資料 | 比較検討中のリード獲得に有効 |
| 無料相談・問合せ予約 | 実際に自社にコンタクトしてもらう導線 | 今すぐ行動したい顕在層 |
| セミナー・ウェビナー参加 | 教育型の施策。参加者を見込み顧客化し、営業ナーチャリングに活用 | 情報収集段階〜比較段階の広い層に対応 |
| 診断・セルフチェック系 | 簡易な質問に答えるだけで自分の課題が可視化される仕組み | 興味関心が高まりつつある読者層 |
メディアの収益化には「PVを増やす」だけでなく、読者の“次のアクション”を明確にデザインする導線設計が不可欠です。
- 成果直結KPIを定義し、効果検証を習慣化する
- 読者の心理フェーズに合ったCTAを複数用意する
- CVポイントは“手軽さ”と“価値提供”を両立させる設計にする
この3点を意識することで、単なる“読むだけのメディア”から、“売上につながるメディア”へと進化できます。
オウンドメディアのマネタイズに失敗する3つのパターン
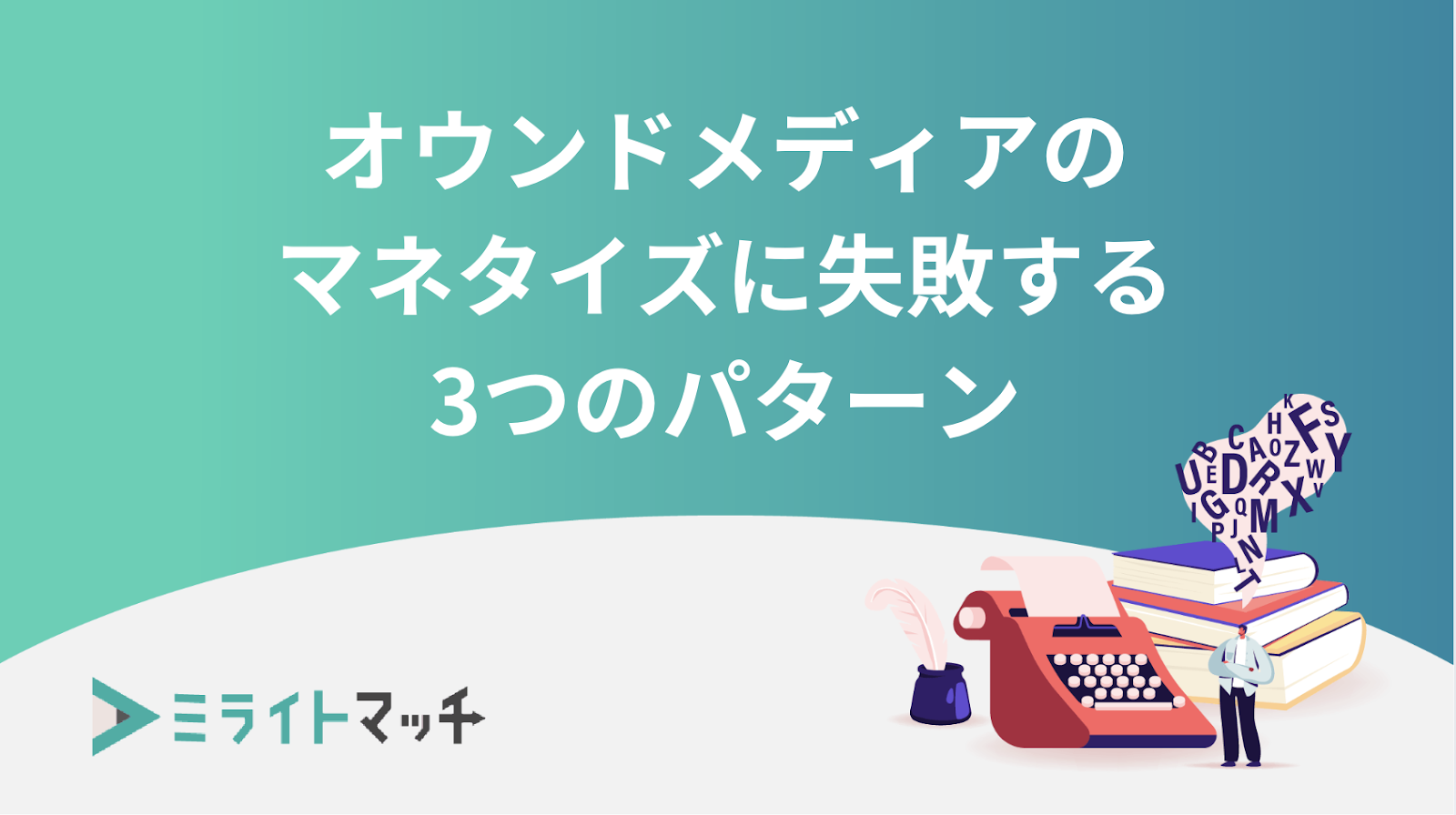
オウンドメディアを立ち上げる理由の多くは、「リード獲得→営業支援→売上貢献」というマネタイズの実現です。
しかし実際には、多くのメディアが「アクセスはあるのに売上に結びつかない」という壁に直面します。
本章では、オウンドメディア運用でよくある“失敗の3大パターン”を解説し、それぞれに対する具体的な改善策を紹介します。
パターン①|営業と連携せず、PVだけ追ってしまう
メディア担当者が「PV=成果」と誤解し、営業部門との連携がないまま記事を量産してしまうパターンです。
結果として、営業が求めるリード属性と異なる層を集客してしまい、「集めても商談につながらない」という状態になります。
【よくある例】
- 営業:中堅〜大手企業の部課長層を狙いたい
- メディア:検索ボリュームが大きい初心者向けワードで集客
このようにターゲットのズレがあると、案件化率が低く、営業の信頼も失いやすいのが実情です。
改善策としては以下が挙げられます。
- 事前に「営業が本当に欲しい顧客像」を明文化
- カスタマージャーニーを共有し、記事内容を“商談の種”に変える
- 記事単位で「この内容は誰向けか」「次に何をしてほしいか」を整理
パターン②|KPI未設定で上司に説明できない
KPIを設定しないまま運用を続けると、「なんとなく頑張っている」状態が続き、成果報告の根拠が持てません。
定例会議で「PVは増えてます」「ブログ本数は順調です」と報告しても、上司は“で、売上は?”と不信感を持ちます。
KPIを設定しないまま運用を続けると、「なんとなく頑張っている」状態が続き、成果報告の根拠が持てません。
定例会議で「PVは増えてます」「ブログ本数は順調です」と報告しても、上司は“で、売上は?”と不信感を持ちます。
【よくある例】
- 数値目標は記事本数だけ。成果は感覚頼り
- 記事がCVや商談にどう貢献したかを可視化できない
改善策としては以下が挙げられます。
- CV数・リード数・CTAクリック数など「行動に紐づくKPI」を設定
- 記事ごとに「どの営業成果に貢献したか」をSalesforceやHubSpotで紐づける
- 上司向けには「売上貢献のストーリー」として資料化
「今月の記事がこの商談につながった」ことを可視化できると、メディアの社内評価は一気に上がります。
パターン③|リードが獲れてもCV導線がない
SEOでリードは集まり始めたのに、「そこから営業につながる流れが設計されていない」ケースです。CV(コンバージョン)ポイントが曖昧、CTAが弱い、資料もないなど、もったいない状態です。
読者が問い合わせしたいと思っても、何をすればいいかわからない状態=機会損失です。
【よくある例】
- CTAが目立たない or 記事と無関係な内容
- ホワイトペーパーが古い or 有用性が低い
- 問い合わせフォームが多すぎて離脱率が高い
改善策としては以下が挙げられます。
- 各記事に明確な1つのアクションを設計(DL・診断・予約など)
- 記事テーマと紐づくホワイトペーパーや事例資料を整備
- 問い合わせフォームは最小限の項目で、スマホ対応を徹底
「読者の次の一歩」が設計されて初めて、メディアは“マーケティングツール”として機能します。
まとめ:オウンドメディアのマネタイズ化は”設計”と”導線”がカギ
オウンドメディアが成果を上げるには、「コンテンツの質」以上に**“売上に向けた導線設計”と“営業との連携”が鍵を握ります。
- 営業部門と連携し、案件化しやすいテーマとペルソナ設計を共有する
- KPI設計で上層部にも“数字で語れる運用”を構築する
- CV導線を記事単位で最適化し、記事 → 商談の流れを明示する
これらを地道に積み上げることで、単なる「読み物メディア」から、「営業を生み出す仕組み」へと進化できます。
監修者プロフィール

- 株式会社IT&Plucktice 代表取締役
-
【プロフィール】
・新卒でアクセンチュア株式会社に入社し、2019年に株式会社IT&Pluckticeを創業
・SEO記事制作現場におけるマッチングの課題感を解決すべく、ライティング人材に特化したマッチングサービス「ミライトマッチ」を立上げ・運営
【実績】
・Webマーケ会社にて、複数SEOメディア事業の立ち上げ、収益化に貢献
・2021年に「ミライトマッチ」をリリースし、1900名以上のフリーランスを集客。企業と人材のマッチング率は約90%を誇る
最新の投稿
- 2025年10月20日インタビュー【導入事例】プロの文章力とインタビュー力が、適切な言語化を実現する
- 2025年9月10日インタビュー【導入事例】社内知見×外部の専門性で、独自性の高い記事制作体制を実現
- 2025年4月30日コラムWebライター直接契約完全ガイド|コスト削減&クオリティアップの方法
- 2025年3月5日オウンドメディア運用オウンドメディアのKPI設定方法:KGIや指標例、効果測定と合わせて解説