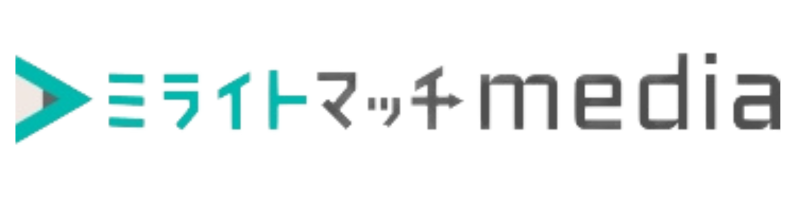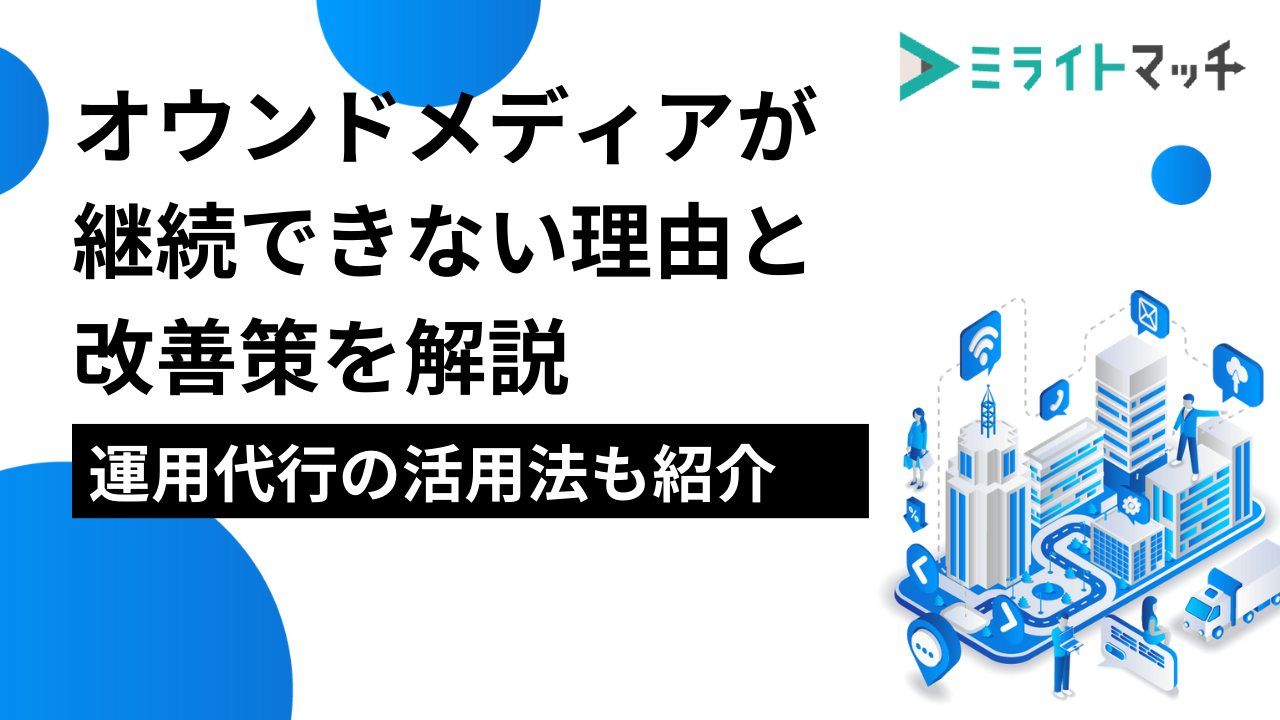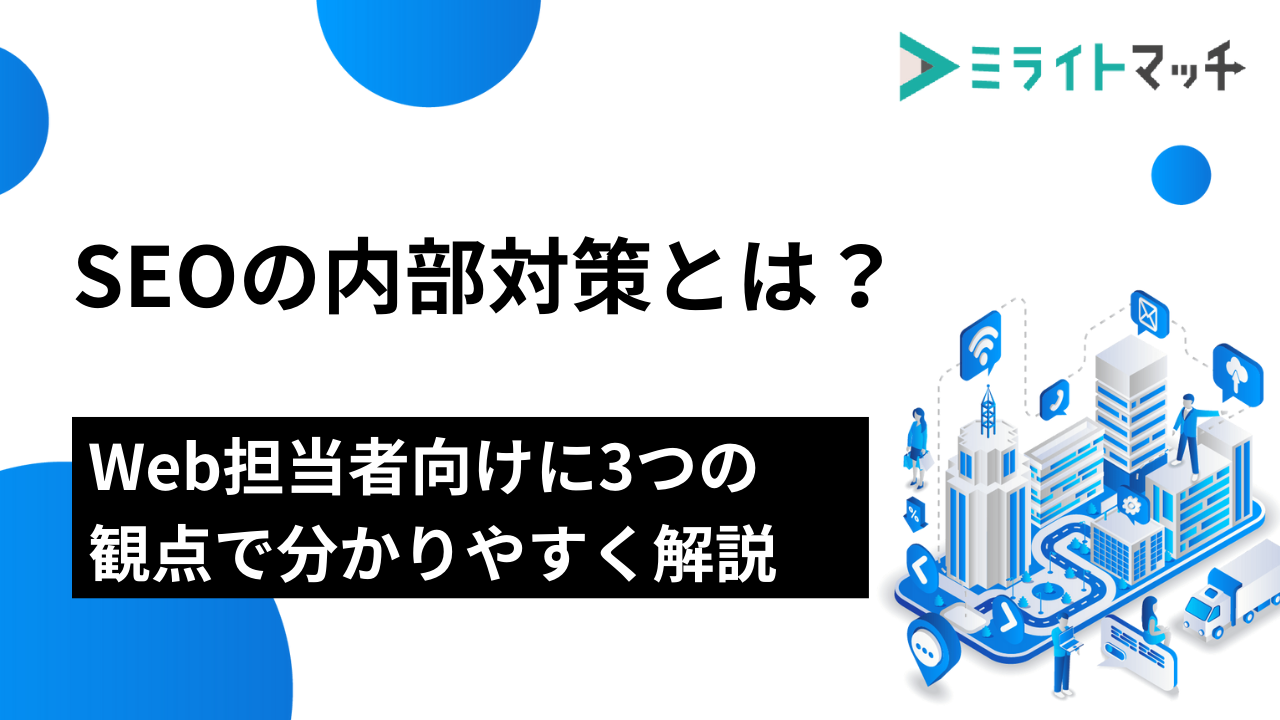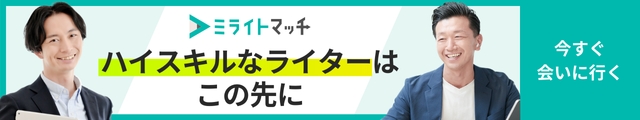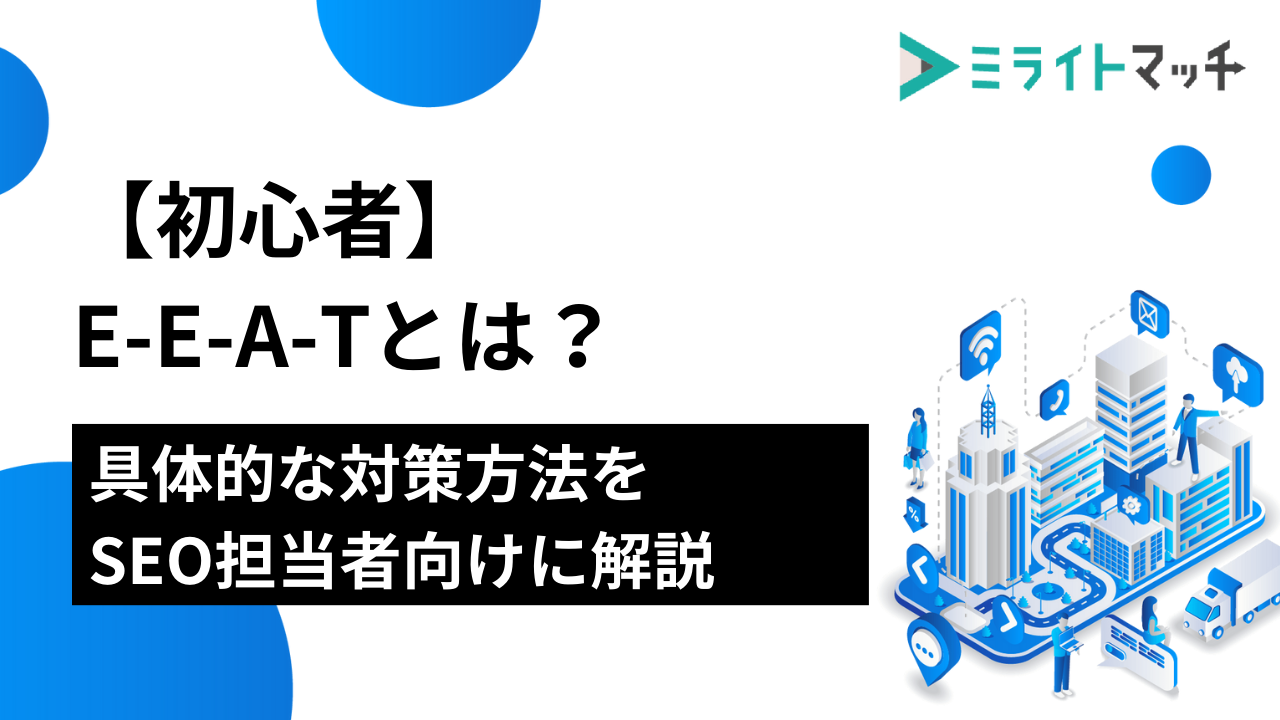
2022年12月、GoogleはE-A-TにExperience(経験)を加え、E-E-A-Tという新しい評価基準を発表しました。
E-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取ったもので、Googleの検索品質評価ガイドラインにおける重要な指標です。

本記事では、SEO対策に取り組む方に向けて、E-E-A-Tの基本概念から具体的な対策方法まで分かりやすく解説します。ぜひご参照ください。
▼この記事でわかること
- E-E-A-Tの基本的な意味と重要性
- GoogleがE-E-A-Tを重視する3つの理由
- 各要素(経験・専門性・権威性・信頼性)の具体的な対策方法
- E-E-A-T対策を意識したオウンドメディア運営のポイント
- 「SEOやコンテンツ制作を外注したいけど、誰が担当するか分からないのが不安…」
- 「専門性が必要な分野なのに、記事のクオリティが期待に届かないことが多い…」
- 「契約期間や初期費用の縛りがあって、気軽に試せないのが悩み…」
そんなお悩みを抱えるあなたへ。【ミライトマッチTEAMS】は、透明性・専門性・柔軟性の3つの強みで、理想のコンテンツチームを作るお手伝いをします!
自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。
【図解あり】E-E-A-Tとは?対策方法

E-E-A-Tとは、Googleが検索順位を決める際に重要視する要素であり、「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」の頭文字を取ったものです。
以前はE-A-Tとして「専門性・権威性・ 信頼性」を重視していましたが、2022年12月15日に新しく「経験」が追加され、現在のE-E-A-Tとなりました。
Google の自動システムは、さまざまな要因に基づいて優れたコンテンツをランク付けするように設計されています。関連するコンテンツを特定した後、最も役に立つと判断されたコンテンツに高い優先順位を付けます。そのために、どのコンテンツが、エクスペリエンス(Experience)、高い専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)、すなわち E-E-A-T の面で優れているかを判断するための要素の組み合わせを特定します。
引用:E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて|Google検索セントラル
E-E-A-Tは検索順位に直接影響するわけではありませんが、順位を判断する指標として重視されているため、SEO対策において考慮しなければなりません。
EEAT①|Experience(経験)

Experience(経験)とは、コンテンツ制作者やウェブサイト自体が、そのトピックに関して実際に経験を持っていることを示します。
例えば、旅行に関するウェブサイトであれば、実際にその場所を訪れた人の体験談や写真などを掲載することで、経験をアピールできます。
経験に対する対策①-1|自身が経験した情報を入れる
ウェブサイトやコンテンツに、自身の経験に基づいたオリジナルの情報を盛り込むことで、ユーザーにとってより価値のある情報提供が可能になります。
例えば、具体的な例として
- 旅行ブログで、実際に訪れた観光地の感想やおすすめスポットを紹介する
- 料理レシピサイトで、自分で作った料理の写真や調理のコツを掲載する
- 商品レビューサイトで、実際に商品を使った感想や評価を詳しく記述する
といった内容が挙げられます。
経験に対する対策②-2|インタビューや取材の情報を入れる
専門家や経験者へのインタビューや取材を通して得た情報をコンテンツに掲載することで、より深い情報を提供し、信頼性を高めることができます。
例えば、具体的な例として
- 実際に商品やサービスを利用したユーザーにインタビューを行い、その感想を掲載する
- イベントやセミナーに参加し、そのレポートを記事にする
といった内容が挙げられます。
以前の記事で、外部にインタビュー記事を外注する際の費用相場について記載していますので、参考にしてください。
▼関連記事
インタビュー(取材)記事を外注する際の費用相場|依頼先別の単価や制作フローについて解説。
EEAT②|Expertise(専門性)

Expertise(専門性)とは、コンテンツ制作者やウェブサイトが、特定の分野において深い知識やスキルを持っていることを示します。
専門性の高いコンテンツは、ユーザーにとってより信頼できる情報源として認識されます。
Googleでは、専門性に関して以下の項目を発表しています。
コンテンツは、明確な情報源、掲載されている専門知識の証左、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(例: 著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示すなど、掲載内容が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供していますか。コンテンツを制作しているサイトを誰かが調査したとしたら、対象トピックの権威としてサイトが信頼されている、または広く認知されているという印象を受けますか。このコンテンツは、確実にトピックを熟知している専門家または愛好家によって執筆され、レビューされていますか。コンテンツに明らかな事実誤認はありませんか。
引用:有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成|Google検索セントラル
このように、明確な情報源を記載することや、専門家や愛好家による監修が専門性によって重要なことがわかります。
専門性に対する対策②-1|自社の得意ジャンルに集中する
自社の強みを生かせる分野にコンテンツを集中させることで、専門性を高めることが可能です。
幅広い分野を扱うよりも、特定の分野に特化することでより深い情報を提供し、専門家としての地位を確立できます。
例えば、化粧品会社であれば美容に関するコンテンツ、不動産会社が、不動産売買や賃貸に関するコンテンツに特化しましょう。
専門性に対する対策②-2|監修者を入れる
コンテンツの内容を専門家に監修してもらうことで、情報の正確性や信頼性を担保することが可能です。
その分野の専門家や有識者に監修を依頼することで、コンテンツの質を高め、ユーザーからの信頼を得られます。
例えば、医療に関する記事を医師、法律に関する記事であれば弁護士に監修してもらいましょう。
EEAT③|Authoriatativeness(権威性)

Authoritativeness(権威性)とは、コンテンツ制作者やウェブサイトが、その分野において信頼できる情報源として認められていることを示します。
権威性の高いウェブサイトは、検索エンジンからの評価も高くなる傾向があります。
権威性に対する対策③-1|執筆者情報やサイトの運営者情報を入れる
コンテンツの執筆者やウェブサイトの運営者に関する情報を明確に表示することで、透明性を高め、ユーザーからの信頼を得ることができます。
具体的には、
- 執筆者の氏名、所属、経歴、資格などを掲載する
- サイトの運営者情報として、会社名、所在地、連絡先などを掲載する
- プライバシーポリシーや免責事項などを明確に表示する
といった施策が挙げられます。
権威性に対する対策③-2|質の高い被リンクをもらう
被リンクとは、他のWebサイトから自分のWebサイトへ貼られるリンクのことです。
検索エンジンはリンク先のサイトを他のサイトから評価されているとみなし、その評価が検索順位に影響します。
他のウェブサイトから質の高い被リンクを受けることで、権威性を高めることができます。
権威性に対する対策③-3|サイテーションを獲得する
サイテーションとは、Webサイトの名前やURLが、他のWebサイトに掲載されることです。サイテーションを獲得することで、Webサイトの認知度向上に繋がります。
学術論文や公的機関の資料などでサイテーションを獲得することで、ウェブサイトの権威性を高められます。
EEAT④|Trustworthiness(信頼性)

Trustworthiness(信頼性)とは、コンテンツ制作者やウェブサイトが、ユーザーから信頼されていることを示します。信頼性の高いウェブサイトは、ユーザーが安心して利用することができます。
信頼性に対する対策④-1|Googleビジネスプロフィールに登録する
Googleビジネスプロフィールは、無料で登録が可能です。
Googleビジネスプロフィールに登録することで、企業情報を公開し、ユーザーからの信頼を得ることができます。
Google ビジネス プロフィールでは、マップや検索などの Google サービスでローカル ビジネスをどのように表示するかを管理できます。実店舗に顧客を迎え入れてサービスを提供するビジネスや、エリア限定でサービスを提供するビジネスを営んでいる方は、ビジネス プロフィールを活用すればユーザーにビジネスをアピールすることができます。Google でのオーナー確認を済ませているビジネスは、ユーザーからの信頼度が倍増する傾向があります。
引用:Google ビジネス プロフィールへようこそ|Googleビジネスプロフィール ヘルプ
Googleは「Google でのオーナー確認を済ませているビジネスは、ユーザーからの信頼度が倍増する傾向があります。」と表明しており、Googleビジネスプロフィールに登録することが信頼性の向上に繋がることがわかっています。
信頼性に対する対策④-2|サイトをSSL対応にする
SSLとは、インターネット上の通信を暗号化して保護する技術です。
SSL対応にすることで、ウェブサイトのセキュリティを高め、ユーザーが安心して情報を入力できます。
WebサイトがSSL化されているかどうかは、以下で確認できます。
- URLがsの付いた https:// で始まっている
- ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されている
自社のWebサイトがSSL化していない場合は、信頼性向上のためにも対応することをおすすめします。
信頼性に対する対策④-3|コンテンツの更新頻度を高める
最新の情報や質の高いコンテンツを定期的に更新することで、ユーザーにとって有益なウェブサイトであることをアピールできます。
古い情報や誤った情報を放置すると、信頼性が下がる可能性があるため注意が必要です。常に新しい情報が書かれているサイトを目指しましょう。
信頼性に対する対策④-4|運営者情報・会社概要を詳しく開示する
運営者情報や会社概要を詳しく開示することで、ウェブサイトの透明性を高め、ユーザーからの信頼を得られます。
会社の基本情報(住所、電話番号、メールアドレス)に加えて、設立年、代表者名、事業内容、実績を記載することで、信頼性を高めることが可能です。
信頼性に対する対策④-5|公的機関のデータを引用する
公的機関のデータや論文は信頼性が高いため、コンテンツの信憑性を高めることが可能です。
政府統計や研究機関のデータなどを引用し、ユーザーにとって信頼できるコンテンツを目指しましょう。
信頼性に対する対策④-6|WHOIS情報を公開する
WHOIS情報とは、ドメインの所有者、管理者、技術担当者などの連絡先情報を含んだドメインの登録者に関する情報のことです。
WHOIS情報を公開することで、ウェブサイトの透明性を高めることができます。
特に金融関連やショッピングサイトでは信頼性が重要であり、WHOIS情報を公開することで読者に安心感を与えられます。
信頼性に対する対策④-7|構造化マークアップを使用する
構造化マークアップとは、検索エンジンがウェブサイトのコンテンツを理解しやすくするためにHTMLなどのコードへマークアップ(=記述)することです。
構造化マークアップを使用することで、検索エンジンがコンテンツ内容を正しく理解でき、評価を高めることができます。
また、リッチリザルト(リッチスニペット)が表示される可能性があることも魅力的なポイントです。
- 「SEOやコンテンツ制作を外注したいけど、誰が担当するか分からないのが不安…」
- 「専門性が必要な分野なのに、記事のクオリティが期待に届かないことが多い…」
- 「契約期間や初期費用の縛りがあって、気軽に試せないのが悩み…」
そんなお悩みを抱えるあなたへ。【ミライトマッチTEAMS】は、透明性・専門性・柔軟性の3つの強みで、理想のコンテンツチームを作るお手伝いをします!
自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。
GoogleがE-E-A-Tを大切にしている理由
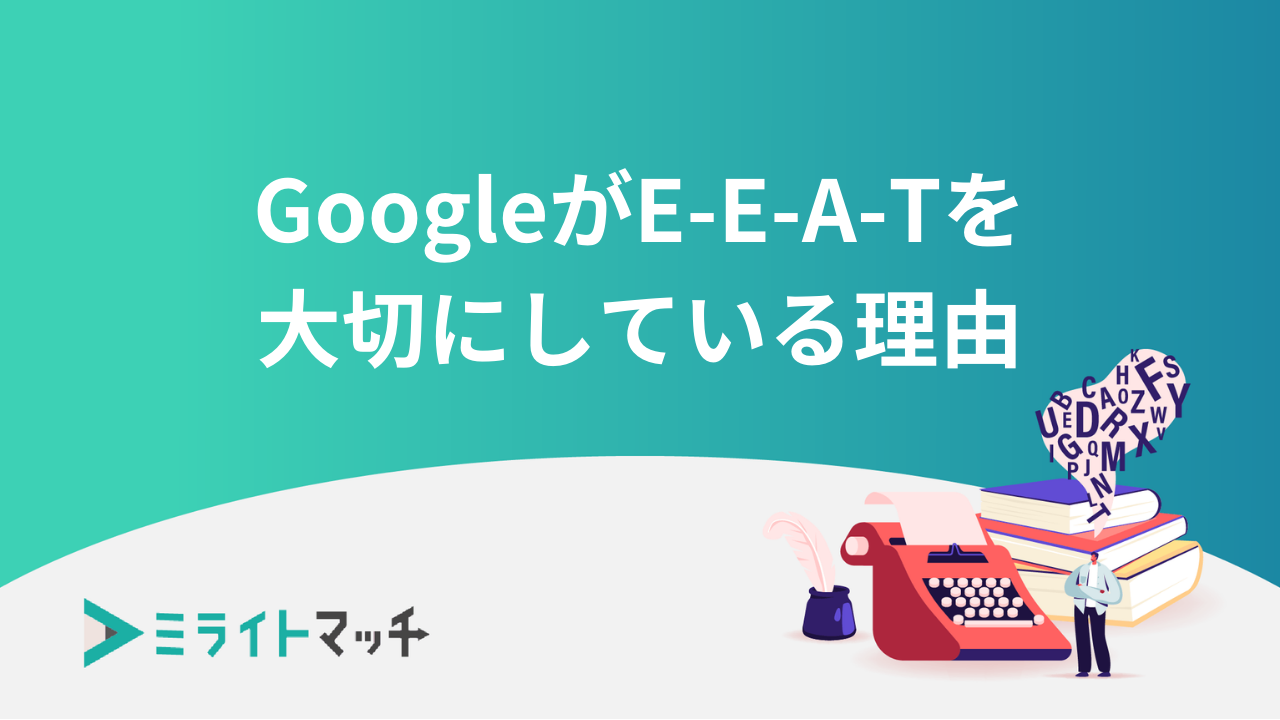
Googleは、ユーザーファーストを第一に考えており、そのためにE-E-A-Tの指標を定めました。
E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-E-A-T が優れているコンテンツを特定できる要素の組み合わせを使用することは有効です。たとえば、Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。
引用:E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて|Google検索セントラル
このように、E-E-A-T自体はランキングに直接影響する要因ではないものの、E-E-A-Tは重要な指標の1つであることがわかります。
ここからは、GoogleがE-E-A-Tを大切にしている理由を3つご紹介します。
▼GoogleがE-E-A-Tを大切にしている理由
- 理由①|品質の高い情報を提供するため
- 理由②|主にYMYL分野で信頼性を確保するため
- 理由③|生成AIを使ったコンテンツに対応するため
理由①|品質の高い情報を提供するため
Googleの使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです。そのため、ユーザーに提供する情報は、正確で信頼できるものでなければなりません。
E-E-A-Tは、ウェブサイトのコンテンツが質の高いものであるかどうかを評価するための基準となります。
Googleは、E-E-A-Tの高いコンテンツを上位に表示することで、ユーザーに質の高い情報を提供することを目指しています。
理由②|主にYMYL分野で信頼性を確保するため
YMYLとは、「Your Money or Your Life」の略で、人の健康や経済状況に影響を与える可能性のある分野を指します。
Googleでは、YMYL領域のトピックについて、E-E-A-Tが優れたコンテンツを特に重視しています。
Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。Google はこうしたトピックを「Your Money or Your Life」、または略して YMYL と呼びます。
引用:E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて|Google検索セントラル
YMYL領域では、誤った情報が人々の生活に重大な影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
過去に、株式会社DeNAが運営していた医療キュレーションサイト「WELQ」が起こした事件をご存知でしょうか。
Googleは以前、専門性や確実性、信頼性よりも記事にどれだけ検索キーワードが入っているかによって検索ランキングを判断していました。そのため、「肩こりは幽霊の仕業」のような科学的根拠の無い医療記事が蔓延し、大きな問題となったのです。
Googleは大規模なアップデートを繰り返しE-E-A-Tが設定され、WELQのようなサイトが現れることはなくなったのです。
このように、YMYL領域では専門家の監修のもと、信頼できる情報を発信することが重要だと言えます。
過去の記事でYMYLについて詳しく記載していますので、参考にしてみてください。
▼関連記事
【初心者向け】YMYLとは?具体的な領域やおすすめのSEO対策7選を紹介
理由③|生成AIを使ったコンテンツに対応するため
近年、文章や画像などを自動生成するAI技術が急速に発展し、ウェブサイトのコンテンツ作成にも利用されるようになっています。
しかし、生成AIによって作成されたコンテンツは、必ずしも質の高いものとは限りません。中には、誤った情報や偏った情報を含むものもあります。
そのため、Googleはコンテンツを適切に評価するために、人間の実体験や専門知識に基づく情報の価値を重視しています。
E-E-A-T対策を意識したオウンドメディア運営のポイント

ここからは、E-E-A-T対策を意識したオウンドメディア運営のポイントをご紹介します。
▼E-E-A-T対策を意識したオウンドメディア運営のポイント
- ポイント①|自社が得意なジャンルで運営する
- ポイント②|ライターや監修者の情報は入れる
- ポイント③|コンテンツ制作の運営体制を整える
ポイント①|自社が得意なジャンルで運営する
E-E-A-Tの中でも特に「専門性」を高めるためには、自社が得意とする分野やテーマに特化したオウンドメディアを運営することが重要です。
幅広いジャンルを扱うよりも、特定の分野に焦点を当てることで、より深い情報を提供し、専門家としての地位を確立できます。
できるかぎり自社事業で取り扱っている商品やサービスのメディアを運営し、自社の強みを活かしたコンテンツを作成しましょう。
ポイント②|ライターや監修者の情報は入れる
コンテンツの信頼性を高めるためには、誰がその情報を作成したのかを明確にする必要があります。そのため、コンテンツの執筆者や監修者に関する情報を掲載することが重要です。
信頼できる人物をアピールするために、プロフィールの内容も丁寧に記載しましょう。
ポイント③|コンテンツ制作の運営体制を整える
質の高いコンテンツを継続的に制作するためには、コンテンツ制作の体制を整えることが重要です。
自社にコンテンツ制作のリソースが無い場合、外注も考慮しなければなりませんが、記事制作を外注に丸投げするだけではうまくいきません。
オウンドメディアの運用を外注する場合は、自社と外注先のハーフ体制で進めるのが効率的なので試してみましょう。
まとめ
今回の記事では、これからSEO対策に取り組む方に向けて、E-E-A-Tの基本概念から具体的な対策方法まで分かりやすく解説しました。
E-E-A-Tは、検索ランキングに直接影響するわけではありませんが、順位を判断する指標として重視されているため、SEO対策において考慮しなければなりません。
特に、人の健康や経済状況に影響を与える可能性のある分野であるYMYL領域ではE-E-A-Tが重視されるため注意が必要です。
ユーザーに安心感を与えるためにも、E-E-A-Tを意識したコンテンツ作りを心がけましょう。
- 「SEOやコンテンツ制作を外注したいけど、誰が担当するか分からないのが不安…」
- 「専門性が必要な分野なのに、記事のクオリティが期待に届かないことが多い…」
- 「契約期間や初期費用の縛りがあって、気軽に試せないのが悩み…」
そんなお悩みを抱えるあなたへ。【ミライトマッチTEAMS】は、透明性・専門性・柔軟性の3つの強みで、理想のコンテンツチームを作るお手伝いをします!
自社にSEOのプロ人材がいないという場合は、ミライトマッチTEAMSの活用をご検討ください。
監修者プロフィール

- 株式会社IT&Plucktice 代表取締役
-
【プロフィール】
・新卒でアクセンチュア株式会社に入社し、2019年に株式会社IT&Pluckticeを創業
・SEO記事制作現場におけるマッチングの課題感を解決すべく、ライティング人材に特化したマッチングサービス「ミライトマッチ」を立上げ・運営
【実績】
・Webマーケ会社にて、複数SEOメディア事業の立ち上げ、収益化に貢献
・2021年に「ミライトマッチ」をリリースし、1900名以上のフリーランスを集客。企業と人材のマッチング率は約90%を誇る