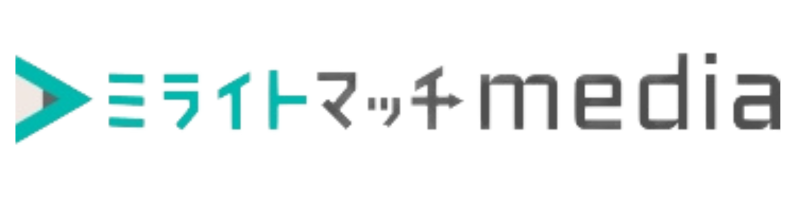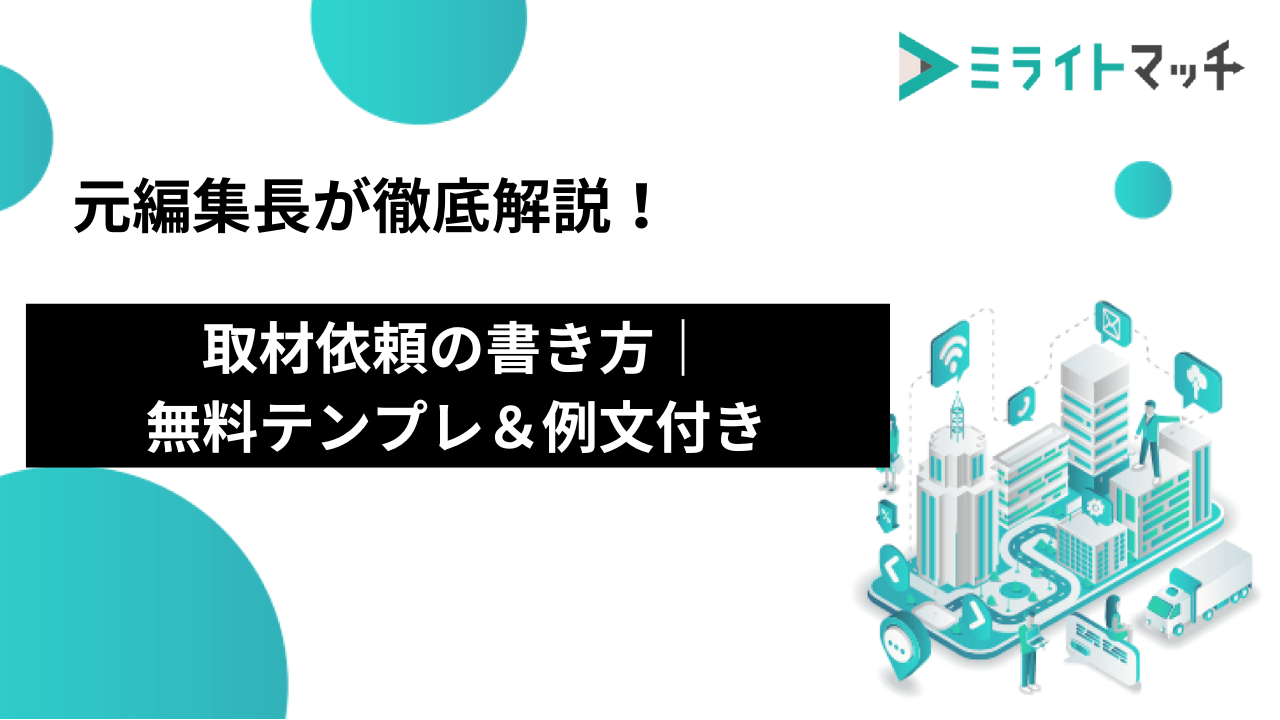
「取材記事を作りたいけれど、依頼の仕方がわからない」「社内にインタビュー対応できる人がいない」
──そんな悩みを抱える広報・マーケティング担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、取材記事をスムーズに進めるための基本的な流れや、依頼書の書き方、注意点、インタビュアーの選び方などをわかりやすく解説します。
取材経験がなくても安心して進められるよう、そのまま使えるテンプレートや現場の声もご紹介。
ぜひ取材依頼~記事作成の参考にしていただければと思います。
▼この記事でわかる内容
- 取材依頼から執筆までの流れ
- そのまま使える取材依頼書のテンプレ
- 取材経験者から学ぶ、気を付ける点ややってよかったこと
- 良いインタビュアー・ライター選定の方法
ぜひ最後まで読み進め、記事作成の参考にしていただければと思います。
取材記事ができるまでの流れ|依頼から執筆
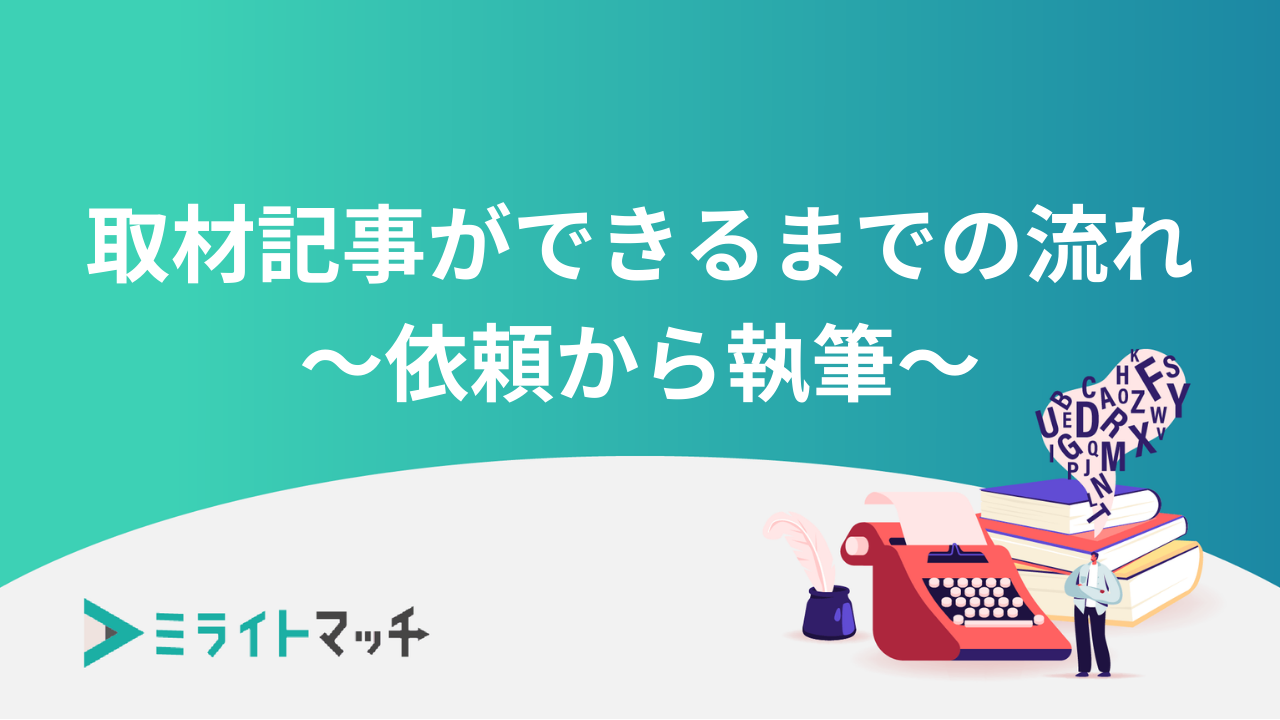
取材記事は企画の立案に始まり、その決まったテーマに沿って取材先(相手・場所)の選定→取材に向けた段取り→取材→原稿執筆→編集→校正(関係各所への確認)→→記事の公開
といった流れで主に行われます。
各プロセスの中で、念入りな準備に基づく「実行力」、現場でのトラブルに動じない「現場力」、記事公開にあたっては内校を行い、誤字脱字の確認や読み手に不快な思いを与えない表現になっているかなど、公開までには多くのことが求められます。
いかに円滑に取材を進めていくか。取材行程はもちろん、どういう取材先を選んでいくべきかを考えていきましょう。
その積み重ねが、読者の心を動かす魅力ある記事づくりへとつながっていきます。
そもそも取材依頼書って何?

取材依頼書とは、取材を行うメディア関係者や企業が、取材対象のお相手や取材場所に対して公式に取材依頼するために提出する文書のことをさします。
取材日や取材の目的、内容、全体のスケジュールを提示し、取材対象者に承諾を得るために、取材に先立って提出を行います。取材目的のみならず、「なぜ取材をしたいのか」という取材における想いや熱意を伝えることで承諾を得やすくします。
取材依頼書は取材対象者に信用・信頼を得るための「第一歩」であり、取材が成功するかどうかの重要なポイントとなります。
筆者もこの取材依頼書の内容によるトラブルを経験した一人です。
特に多かったのが撮影に関する行き違いです。
撮影予定の場所で撮影ができない、撮影予定の商品が用意いただけていない、その結果、現場での変更を強いられたことがあります。
また記事の内容においても、こちらの聞きたいお話が「業界的なお話」にも関わらず、取材対象者からは「お店のPRのお話」に終始されたことも。
これらは、取材依頼書による「伝えた」「聞いていない」の行き違いの部分です。理想なのは、取材依頼書の提出で終わるのではなく、取材の事前にしっかりすり合わせを行うこと。お互いの”ズレ”が起こらないよう対策をしたいところです。
適切で正確で簡潔・分かりやすい依頼書を提示することは、取材の円滑化につながるだけではなく、相手への配慮や取材に対する想いを伝えられます。
反対に取材依頼書に漏れや抜け、不明確さや表現の不適切さがあることは取材対象者への不信感につながるだけではなく、上記のように取材や記事作成のスムーズさも失われることになります。
良い記事を作るための逆算として、まず慎重に行うべきプロセスの一つです。
失敗しない取材依頼書の書き方
取材依頼書は、依頼相手に誤解なく意図を伝えるための重要な書類です。
正しい書き方を知っておけば、依頼の通りやすさや取材の質も大きく変わります。
この記事では、正しい依頼書を作成するために押さえておきたいポイントを解説し、さらに以下の流れで実践的な内容をご紹介します。
このセクションで紹介すること
- 取材依頼書作成のポイントと注意点
- そのまま使えるテンプレート
- 依頼文の書き方
- シーン別の例文集
取材依頼書作成のポイントと注意点
取材依頼書を作成する上で、次の点に気をつけていきましょう。
・「取材目的の詳細を明確に伝える」
今回の取材がどのような目的で行われるのか、どの媒体(メディア)にて掲載されるのか、取材の形式(オンラインでも可能なのか?)はどういう形か、取材時間はどのくらいか、など伝えるべき詳細は細かく伝えましょう。
・「5W1Hを意識する」
WHEN(いつ) WHERE(どこで)WHO(誰が) WHAT(何を)WHY(なぜ) HOW(どのように)の「5W1H」の情報を漏れなく記載しましょう。
特にWHATやWHYといった目的の部分については、相手との相違が生まれやすい部分であるので、確実に明記するようにしましょう。
・「取材相手への配慮を忘れない」
相手は、取材のために業務を止めて時間を割いてくれます。滞りのないように、事前に把握できることはしっかりヒアリングし、詳細を記入しましょう。
取材日についても、日程や時間をいくつか提示することで、負担を減らしてあげることが出来ます。こちらでできる最大限の配慮を忘れず行いましょう。
そのまま使える!取材依頼書テンプレ
取材前に伝えるべき情報は、取材依頼書内にまとめて記載します。できるだけ詳しく、しかし簡潔にまとめることで相手に負担やストレスを与えずにすみます。
以下がテンプレートとなります。
取材依頼書テンプレ
令和〇年〇月〇日
(または)2025年〇月〇日
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇様
株式会社〇〇
〇〇部(部署名)
〇〇 〇〇(担当者名)
———————————————————————————
取材のご依頼について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社が運営しておりますWebサイト(情報誌/広報誌/会報誌 SNS 等)にて、〇〇をテーマとした特集記事を企画しており、貴社(または〇〇様)にご登場いただきたく、下記の通り取材をお願い申し上げます。
ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
■取材概要
媒体名:⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎
掲載予定:2025年〇月〇日頃
取材目的:〇〇に関する活動・取り組み・ご経験等のご紹介
想定読者層:〇〇(例:20〜30代のビジネスパーソン)
取材形式:訪問にて(オンラインなど)
取材時間:約〇〇分
取材希望日程:〇月〇日〜〇月〇日の間で調整
撮影の有無:あり/なし(※ポートレート/現場写真 等)
掲載前の原稿確認:可能(事前に確認用原稿をお送りします)
上記に関しまして、ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
何卒ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
【ご連絡先】
株式会社〇〇
〇〇部 (氏名)〇〇 〇〇
TEL:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
Mail:〇〇〇〇@〇〇〇〇.co.jp
URL:https://〇〇〇〇.co.jp
取材依頼文の書き方
取材が成功するかどうかは、はじめのアプローチである「取材依頼文」の出来によって大きく左右されるといっても過言ではないでしょう。相手に安心感と信頼を与え、協力してもらえるような依頼文を制作することを心がけましょう。
まずは取材者自身の自己紹介から。誰からの依頼であるか、会社名や担当者名、連絡先などの基本情報を記載します。
次に取材の目的や記事の掲載媒体、想定している読者層、記事のテーマなどを簡潔に記載します。
取材形式(対面・オンライン)、所要時間の目安、希望する日程の候補など、具体的な情報を提示すると、相手もスケジュール調整しやすくなります。写真撮影の有無や、公開前の確認の可否などもあらかじめ記載しておくと親切です。
丁寧で誠実な依頼文は、相手の安心につながり、快く取材に応じてもらえる可能性が高まります。
郵便、メール以外で送る場合
昨今では、LINEの利用率が90%を超えて(LINEリサーチ記事参照:https://www.lycbiz.com/jp/service/line-research/)おり、連絡手段としては一般化されております。
しかし「プライベート」と「ビジネス」とで分けて考えられる方もおり、いくら繋がりやすいからとはいえ、LINEを使うことに抵抗を持たれる方も一定数おります。
ビジネス向けでいえば、SlackやChatwork、FacebookのMessengerなどビジネスで利用されるアプリは数多くあります。
依頼する側としては繋がりやすく、確実に見てもらえることが大前提ではありますが、連絡手段については相手の意向を汲んであげると良いでしょう。
これは、SNSのDMについても同様に言えます。InstagramやXなど本人に直接、気軽にコンタクトができるようになりました。
もしかすると、ビジネスマナーといった改まった形式でのやり取りが求められるメールよりも、現代の方はメッセージでのフランクなやり取りの方がやり易さがあるかもしれません。
これも相手次第の部分で、お一人お一人に合わせた状況が求められます。依頼側としては、どのような状況においても臨機応変に対応できるようにしておくと良いでしょう。
メッセージ系アプリも資料の添付は可能なので、PDFや画像データにして送付ができます。
メールへの直接記載同様に、メッセージ内に記入することも一つではありますが、縦長になり、長たらしい印象を与えてしまうこともありますので、注意が必要です。
シーン別・依頼文の例文集
取材相手や、状況に応じて文面の使い分けを行うと良いでしょう。
よくあるシーンを想定した、依頼文の例をご紹介します。
- 初めて取材を受ける取材対象者の場合
- 取材経験のある方への依頼を行う場合
- オンラインで依頼を行う場合
- 急ぎでの依頼となる場合
1.初めて取材を受ける取材対象者の場合
件名:取材のご依頼(〇〇メディア/テーマ:〇〇について)
〇〇株式会社
広報ご担当者様
突然のご連絡、失礼いたします。
〇〇メディアを運営しております、株式会社〇〇の〇〇と申します。
現在、〇〇をテーマにした特集記事を企画しており、
ぜひ貴社の〇〇に関する取り組みを取材させていただきたく、ご連絡させていただきました。
以下、取材の概要をご確認いただき、ご検討いただけますと幸いです。
(※以降、媒体名・日時・所要時間・形式・確認の流れ などを記載)
2.取材経験のある方への依頼を行う場合
件名:再度のご取材のお願い(〇〇メディア)
〇〇様
平素より大変お世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。
先日は取材にご協力いただき、誠にありがとうございました。
今回は新たな企画「〇〇」の中で、再び〇〇様のお話をぜひ伺いたく、
ご連絡差し上げました。よろしければ
以下の日程候補の中からご都合の良い日時をお知らせいただけますと幸いです。
3.オンラインで依頼を行う場合
件名:オンライン取材のご依頼(〇〇メディア)
〇〇様
突然のご連絡、失礼いたします。
〇〇メディアを運営しております、株式会社〇〇の〇〇と申します。
現在、〇〇をテーマにした特集記事を企画しており、
ぜひ貴社の〇〇に関する取り組みを取材させていただきたく、ご連絡させていただきました。
お忙しい中恐縮ですが、オンライン(Zoom または Google Meet)にて、
30〜40分程度のインタビューをお願いできればと考えております。
可能な範囲で構いませんので、ご検討いただけましたら幸いです。
4.急ぎでの依頼となる場合
件名:【急ぎのお願い】取材のご協力について(〇〇メディア)
〇〇様
突然のご連絡、大変失礼いたします。
〇〇メディアを運営しております、株式会社〇〇の〇〇と申します。
現在、〇月〇日公開予定の特集記事を制作しており、大変急ではございますが、
〇〇様の活動についてぜひ取材させていただきたく、ご相談させていただきました。
ご多忙の中恐縮ではございますが、〇月〇日〜〇月〇日までの間で、
30分〜1時間程度のお時間を頂戴できましたら幸いです。
オンラインでも対応可能です。
お引き受けの可否を含め、ご検討いただけましたら幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
現場から学ぶ!取材依頼時の注意点とは?
取材は、事前準備がすべてと言っても過言ではありません。取材依頼で「伝えたつもり」が伝わっていなかった時、それはトラブルのもとになります。情報不足や確認の漏れは、相手の機嫌を損ね、信頼関係を崩すことにもなりかねません。より丁寧な対応が求められます。
もし、掲載する媒体の内容や目的が十分に伝わっていないと、「聞いていた内容と違う」「質問が想定外な内容だった」といったいき違いが起こります。また、取材後の記事作成から確認までの流れを事前に伝えていなかったことで、公開する寸前に修正が入り対応しなくてはならず、掲載までのスケジュールに支障をきたすこともあります。
写真撮影についても必ず確認しましょう。当日撮影しようとしたら、撮影NGと言われてしまう場合もあります。当日その場で「撮ります」と伝えるのではなく、取材前に必ず確認しておくべきでしょう。
スムーズで信頼される取材を行うためには、前途した5W1H「何を」「どこまで」「どのように伝えるか」を丁寧に設計することが重要です。相手の立場に立った、誠意ある依頼こそが、良い取材記事づくりの第一歩です。
実体験から学ぶ|取材経験者のリアルな声

実際の現場で取材を行う経験者の皆さんにはどのような苦労があるでしょうか。
実際に取材経験をしてきたからこそ分かる、リアルな声をお届けします。
現場で気をつけていること・やって良かった工夫
お会いする方は、当然初めてお会いする方ばかり。最初の印象は、その後の取材の行末を決めるといっても過言ではありません。丁寧に、明るく朗らかに取材対象者と接します。取材の最初から終わるまで、記事のOKを頂くまで気を抜きません。
常に「十分すぎるくらいに丁寧に」を心がけています。このことはライターの先輩から教わった、私の中で大事にしていることです。
そして「段取り力」と「現場力」は大いに求められると思います。これは訪問した場合になりますが、どこでどのように取材を進めるか、現場に入った瞬間から、事前のヒアリングをもとにあらゆる想定を考えます。
また撮影が必要な場合は画角はどうするか、撮影のために場所の確保も行います。他にスタッフがいれば良いですが、大抵は少人数で対応することのほうが多いです。
状況によっては相手先にも協力していただきながら、スピーディーに段取ります。ここでもたついてしまうと、相手に不安しか与えません。動じず、平然とこなすことが重要であると思います。よりよく魅力を引き出す記事にするためには、ライターとしてではなく「ディレクター」としての能力も必要だと思います。取材現場は想定外のことばかり、予定通りのことのほうが圧倒的に少ないです。「何か起こる」「思い通りにはいかない」と心構えていたほうが、意外とすんなりいきます。
これも自らの度胸や重ねてきた経験の賜物ですね。ディレクターとして全体を見渡して、現場でより良い判断をしていきます。
準備ができれば、次は相手に話しやすい雰囲気を作ります。リラックスしてお話いただけるように、他愛のないお話をしながらコミュニケーションをとり、相手の心の壁を取り外し、現場の空気を温めます。温めるといっても特別なことは必要ないと思います。笑いを取るなんてことも必要ないです。
相手は「取材」というだけでどこか構えてしまう。取材ではなくただの「会話」と思っていただけるほうが、思っていることや考えていることを引き出しやすくなります。相手の心の壁を外すには、自らが外すこと、これも先輩に教わりました。共通点や共感できることを引き出せると親近感が湧きます。私自身、多趣味というわけではないですが、スポーツや芸能、トレンド、最近会ったニュースなどはテレビやWEBニュース、SNSなどで取り入れるようにしています。
何かしらおさえておけば、会話に困ることもありません。取材相手の専門的な用語や知識を知ることも大事ですが、会話の引き出しを増やしておくことも大切です。
(元情報誌編集長 Yさん)
依頼者に事前に伝えてほしいこと
取材対象者への情報共有はしつこいくらいに密に行います。取材対象者が「そんなことは聞いていない」ということにならぬよう、丁寧な情報共有が必要だと思っています。
取材対象者が当日安心して、本音でお話しいただけるような環境作りをすること、取材の成功のためにはそれが重要です。事前に取材の目的、掲載媒体、記事の完成イメージをできうる限り伝えています。どの読者に向けて、どういう内容の記事にしていくのかがわかれば、取材対象者も話しやすくなり、もし話が脱線してきても、軌道修正しやすくもなります。
取材の流れ、所要時間も大枠の目安としてお伝えしています。心構えと準備ができ、取材の質は格段に上がりますね。
写真撮影が必要な場合も事前に伝えます。当日、いきなりお伝えしてしまうと、それこそトラブルの要因となります。写真はSNSで使用する場合もあるかと思います。
被写体としての撮影を行う場合、撮られることに抵抗がある方も多くいますので、あらかじめ伝えておく必要があります。細やかな配慮が取材対象者との信頼を築き、より良いコンテンツ作りに繋がります。”十分すぎるくらい”の事前準備を私は行うようにしています。
(広告代理店営業&編集者 Sさん)
取材の成否を左右する!インタビュアー選びのポイント
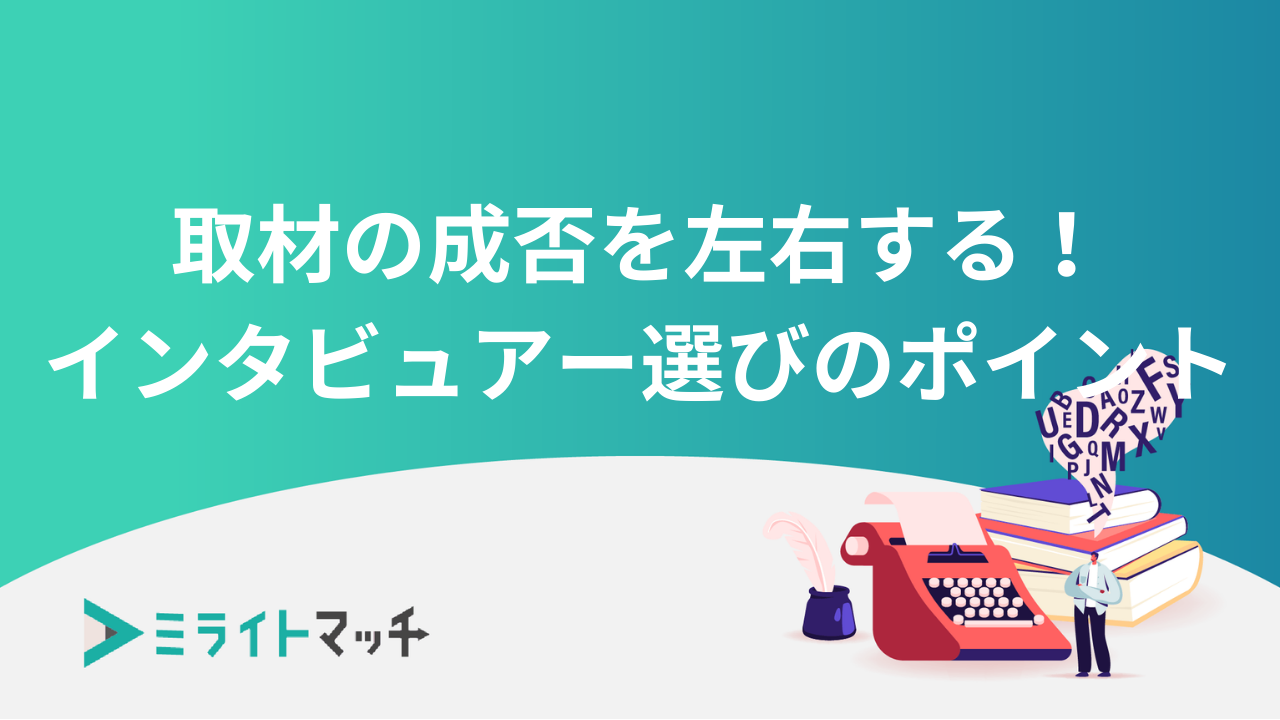
取材の成果を出すためには、インタビュアーの力量に大きく左右されます。どんなに取材対象者が魅力的に話をしても、インタビュアーの質問力や対応力が不足していると、引き出せる情報も限定的になります。
逆に、経験豊富で信頼できるインタビュアーが対応することで、取材対象者の自然と引き出される言葉や想いが表れ、読み手の心に響く記事作りにつながっていきます。
「誰が聞くか」は、とても重要です。
では、良いインタビュアーとはどのような人なのでしょうか? そして、どうすればそうした人を見つけることができるのでしょうか。
良いインタビュアーを見つけるには?
まず、インタビュアーには「聞き手」としての基本的な資質や能力が備わっていることが前提として必要となります。
ベースとなる質問から会話を始め、相手の話を聞きつつ、流れの中でより深く、的確な質問を投げかけられるかどうか。これは「質問力」とも言えますが、「空気を読む力」や「相手のペースに合わせる力」とも言えるでしょう。
現場の空気を温めて、相手が話しやすい雰囲気を作り、自然に本音を引き出せるかどうかが、良いインタビュアーとして大切な部分です。
また、取材に向けた念入りな準備ができるのかも見極める上でのポイントです。取材対象者や記事テーマについてのリサーチを行い、差し支えのない、俗にいうマニュアル的な質問ではなく、深い質問ができる人は、やはり信頼をおけるでしょう。
型にはまった問いではなく、「この人なら話してもいい」「この人ともっと話をしたい」と思わせるような人間性や、目線や頷きなど聞く姿勢ができているか、共感や理解を伴った問いかけができる人材を選びたいところです。
取材現場での経験値の高さも重要な要素のひとつでしょう。場数を踏んでいるインタビュアーは、取材対象者も様々に対応してきています。
男性女性、年齢問わず柔軟な対応ができます。急な話題転換や、想定外の発言に対しても冷静に落ち着いて対応できるのは、経験によるものと言えるでしょう。相手が気を許してくれると、ついメインのお話から脱線しがちになります。そこを戻す力も、インタビュアーの力量といえます。
では、そんな理想的なインタビュアーを具体的にどう探すか。そのポイントとしては過去のインタビュー記事をチェックし、そのインタビュアーの名前を確認するのがひとつの方法です。
また、もし信頼できるライターや編集者がいる場合には、その方から紹介を受けるのも有効です。インタビュアーは記事を読む方にとっては見えにくい存在ですが、“見えないけれど記事の質を大きく左右する存在”であります。信頼できるネットワークを活用して良い方を探していきましょう。
インタビュアー選びは取材の成功に向けて重要な工程です。誰に話を聞いてもらうか、その選択により取材の質も記事の深さも大きく変わってきます。相手を理解し寄り添い、誠実に丁寧に興味深く相手の話に耳を傾けることのできるインタビュアーを見つけること。より良い記事づくりの第一歩となります。
取材依頼は自社or外注?
取材を自社スタッフで行うのか、外注に依頼をするかは悩みどころです。それぞれにメリットとデメリットがありますので、目的に合わせて依頼をするのが良いでしょう。
自社の場合
自社で行う最大のメリットは、自社の想いが素直にダイレクトに伝えられる点にあります。自社を理解したスタッフ取材を行うので、目的や掲載意図をより正確に説明できます。スケジュール調整や事前の内容確認も社内で完結できるため、その柔軟性は大きなメリットです。
一方で、取材経験の浅さは、質問力に不安が残り原稿への落とし込みにも不安が残ります。少なからず経験が必要な役割になりますので質問力、取材力、文章力を鍛えていく必要はあるでしょう。
外注の場合
外部パートナーに依頼する場合、取材・原稿作成の経験をしてきたプロに任せることができるため、質の高い記事コンテンツの制作が期待できます。また、記事のテーマによっては「第三者的な視点」が求められます。客観性のある取材を行うことが可能です。
ただ、外注先には自社や業界への知識・理解が求められます。媒体の目的や読者層、自社の意図などを丁寧にできるだけ正確に共有しないと、方向性がずれてしまう可能性もあります。
取材依頼はミライトマッチ!

取材記事を依頼をするなら、ミライトマッチがおすすめです。
ミライトマッチは、豊富な現場経験と知識を併せ持つライターを抱え、丁寧なサポートを提供することで、クライアントのニーズに合った最適なライターを見つけることができます。
ミライトマッチでは全国に約1200名の取材ライターが登録しており、経営者や著名人などのトップインタビューから自治体イベントの記事作成まで幅広いジャンルで、専門性を持ったライターによる記事作成が可能です。
過去の取材記事の事例や取材ライターの検索はこちらからご覧いただけます。
ご要望に合わせて最適なライターをご紹介いたします。
ライター募集やお見積りも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
その中でも今回は3名のライターさんを紹介します。
T.Oさん
経歴・実績:
・企業取材、ビジネス取材に特化し、取材ライターとして7年目。
・年間100件以上の企業取材を担当。
・現地取材では当日の仕切りから香盤表の作成、エンドクライアントとのやりとり等、ディレクターの動きも対応。
K.Yさん
経歴・実績:
・ライティング、ディレクション歴15年以上で、取材歴は6年
・取材・インタビューは芸能・採用ジャンル合わせて100本以上
・インタビューされ慣れていない方からもお話を引き出すこと、相手の方の魅力を伝える原稿にすることを得意とする
Y.Mさん
経歴・実績:
・取材ライター歴25年
・某有名旅行情報誌で20年間継続して取材を担当
・地域の良さを伝える町記事や観光記事の取材執筆を強みとしている
・年間の取材件数はのべ1000軒
まとめ|満足度の高い取材記事にするために
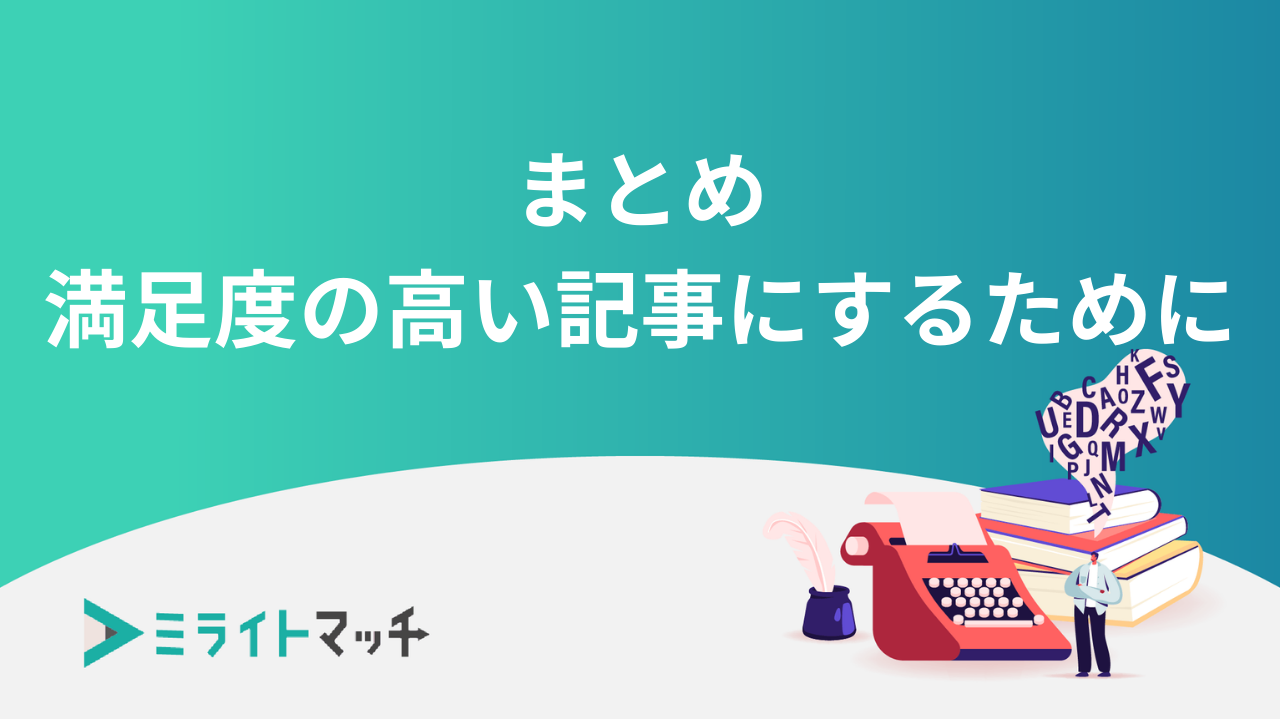
満足度の高い取材記事をつくるためには、誰に何を伝えるかということだけではなく、「どのように伝えるか」が重要です。企画内容、取材先の選定とアポ取り、依頼方法、インタビュアーの選定(自社・外注・その他)、そして取材後の編集や校正まで、公開から公開後までひとつひとつのプロセスに丁寧さと工夫が求められます。
取材対象者と信頼関係を築く一歩として目的や内容、取材方法をわかりやすく・明確に伝えることで、安心して取材に応じてもらうことができ、やり取りもスムーズになります。
準備をしっかり整えたうえで、予定外の事態にも冷静に対応できる“現場力、相手に寄り添う姿勢”も忘れてはいけません。これらは記事の質を左右します。
全ての過程において、「伝える相手」と「取材される相手」の両方に配慮することが、記事を読んでくれる多くの人の心に届く、信頼性のある魅力的な記事づくりにつながります。
最善の準備と誠実な姿勢が、成果を最大化します。
ぜひこの記事を参考に取材記事を作成していただければと思います。